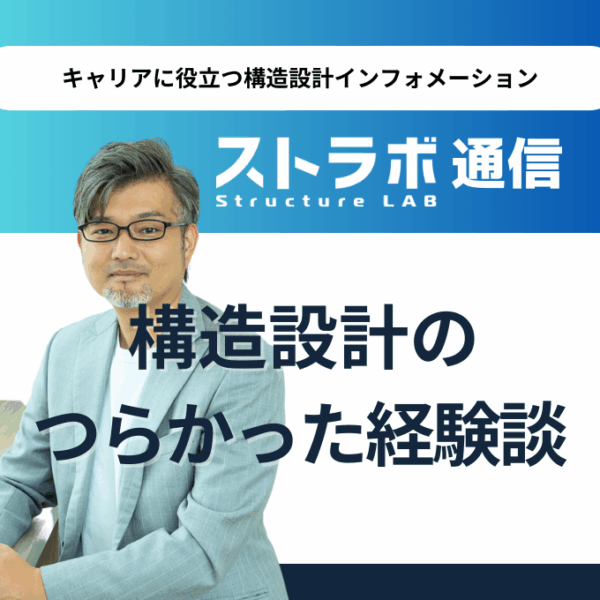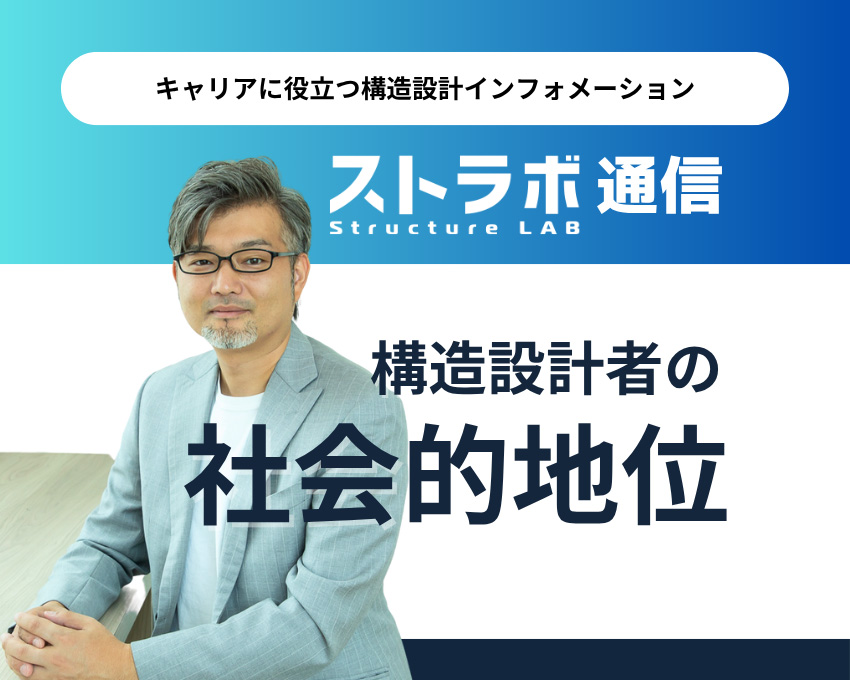
こんにちは!現役の構造設計者であり、株式会社ストラボ代表の小林です。
今回の「ストラボ通信」では、「構造設計という仕事の社会的評価」について、皆さんと考えていきたいと思います。
私自身、20年以上にわたり構造設計に携わってきましたが、この仕事には、社会からもっと評価されるべき価値があると強く感じています。
構造設計者の皆さんが、その価値を実感できる未来を目指して、私たちストラボができることは何か。私の想いを交えながらお話しします。
あなたにとって構造設計者の社会的地位は高い?低い?
「社会的地位」という言葉を辞書で引くと、「社会の中に確立された、人々の名誉や威信を伴う位置」となっています。
一般的には、医師、弁護士、税理士、スポーツ選手などが「漠然と偉い」といったイメージで思い浮かぶかもしれません。
では、私たち構造設計者の社会的地位は高いと思いますか?低いと思いますか?
私は「低い」と感じています。
- 「上司は厳しいし、業務の責任が重すぎてつらい」
- 「意匠設計や設備設計との調整がつらい」
- 「誰にも褒められなくてつらい」
- 「残業が多く、休みが少なくてつらい」
など、構造設計者が抱えるつらさは多岐にわたります。
こう言いたくなる皆さんの気持ちは、よくわかります。構造設計を20年以上続けてきた私自身も、同じような思いをしてきました。
建物や人命を守るという重大な責務を担う仕事であるにもかかわらず、その社会的な認知や評価が十分に得られていないと、私自身も肌で感じています。
例えば、「有名な建築家といえば?」と質問して、ほとんどの場合、意匠設計者の名前ばかりが挙げられるのは、その典型的な例でしょう。
そもそも、2005年に起きた構造計算書偽造問題より以前は、構造設計者が図面に自分の名前すら書けない時代でした。
その頃に比べれば改善された点は確かにあるかもしれません。
ですが、私はまだまだ十分にはほど遠いと考えています。
なぜ、構造設計者の仕事は正しく評価されにくいのか?
なぜ、私たちの仕事は正しく評価されないのでしょうか?
困ったことに「構造設計は計算なんだから誰がやっても同じ!」と考えている人が建築業界の中にも多く存在します。
ですが、実際には構造設計者の技術力によって建設コストや建物の安全性が大きく変わるんですよね。
構造躯体だけでも20%ものコスト変動が生じることがあるのに、「誰に構造設計を頼むか」という要素が軽視され、設計料は低く抑えられる傾向にあります。
私は、この「誰に頼んでも同じであると考えていること」と「設計料は極力安くすることが大事であるという認識」こそが、構造設計者の本当の価値が社会全体に伝わらない根本的な原因だと考えています。
構造設計者の「本当の価値」を社会に広めるために必要なこと
では、私たち構造設計者の価値が正しく評価されるためには、何が必要なのでしょうか?
私はまず、「構造設計」というものがどういったもので、暮らしや社会にどのような影響を与えているのかを、社会全体、そして建築業界全体にも正しく理解してもらうことが不可欠だと考えています。
具体的には、以下のような取り組みが必要になるでしょう。
- 構造設計という職種やエンジニアが建物に与える影響も含めた認知の向上
- 構造設計者としての技術力の向上と、個々が持っている技術の共有
- 構造技術者が人生の各ステージで直面する課題の解決
ですが、これらを実現するのは、個人レベルの活動では到底不可能です。
だからこそストラボは、構造設計者の皆さんが集い、学び、互いのスキルを共有し合える場を提供することで、一人では難しい業界改革を、皆さんと力を合わせて成し遂げられるプラットフォームを創り上げようとしています。
「どう成長したいか」「どう仕事に喜びを見出すか」は人それぞれ違うでしょう。
ですが、私は構造設計者という職種に対して期待や充実感を持てる社会にしたいと願っています。
ストラボは、構造設計者が状況ごとに最適な選択ができるようサポートし、「この人に設計を任せたい」と信頼され、エンジニアとして正しく評価される未来を目指します。
今後も「ストラボ通信」では、構造設計者の現状分析や特有の悩みなど、構造設計に関する様々な情報を発信していきます。
またお会いしましょう!
執筆者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。
関連記事一覧
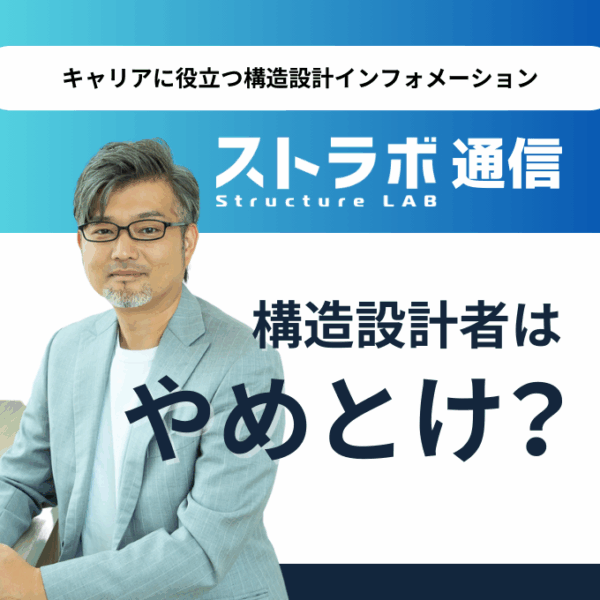
構造設計者はやめとけ!?現役構造設計者が業界の実態を見つめ直す

【ユーザーの声紹介】人手不足を解消し働き方を柔軟にするマッチングサービス|ス...

構造設計の研修は「経済設計」に役立たない?1万件のノウハウを活用した新しい教育...
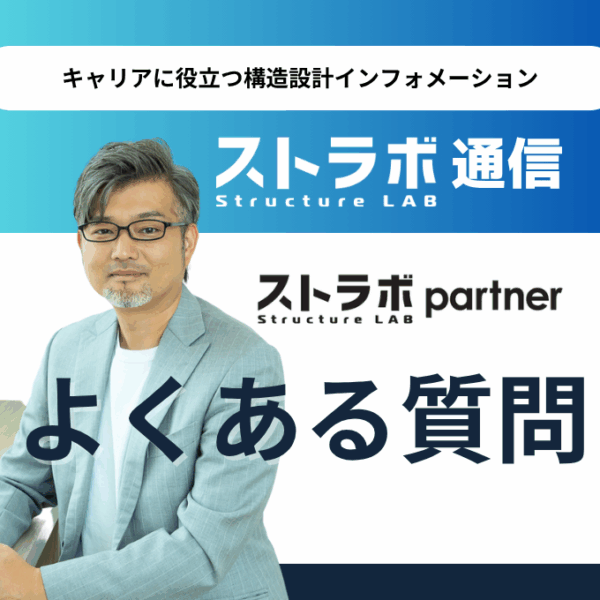
【構造設計を副業にしたい人必見】これが知りたかった!ストラボpartnerのよくある...
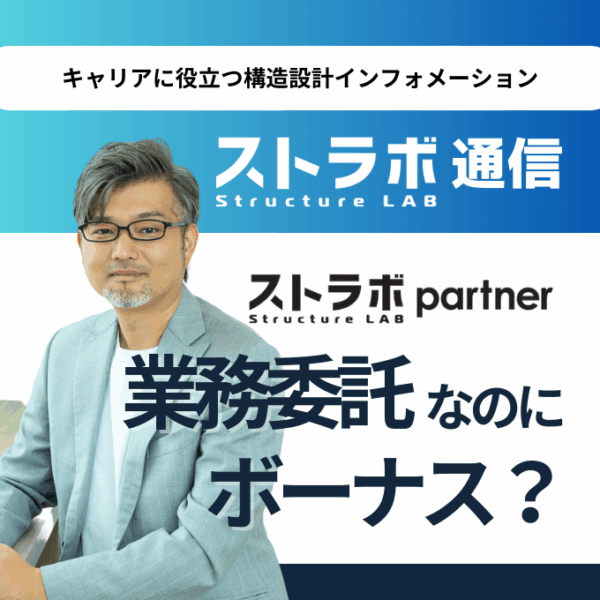
業務委託なのにボーナスあり!副業・独立後に安定収入を即確保|ストラボpartner
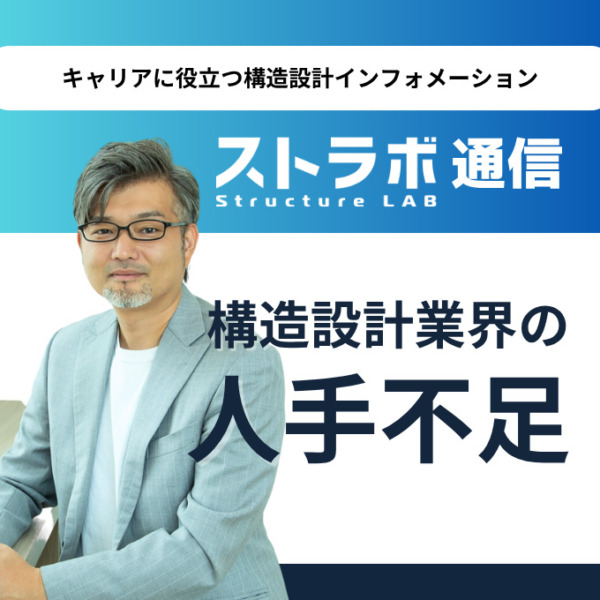
人手不足を逆手に取る!構造設計者だからこそのキャリアアップ戦略
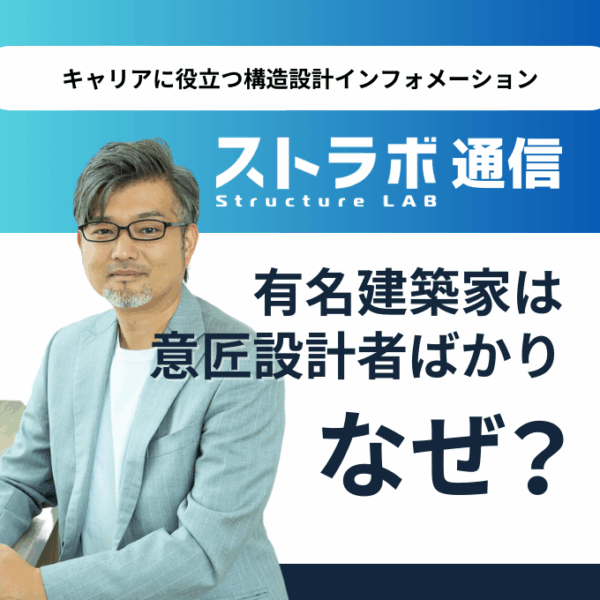
有名建築家が意匠設計者ばかりなのはなぜ?構造設計者が社会に認知されるには