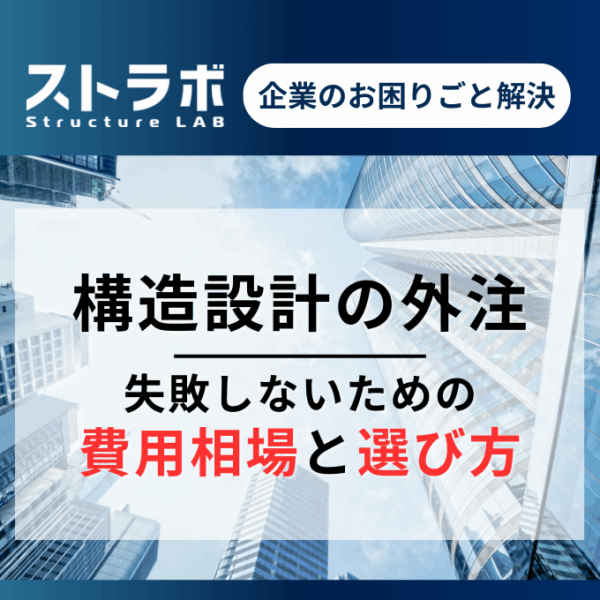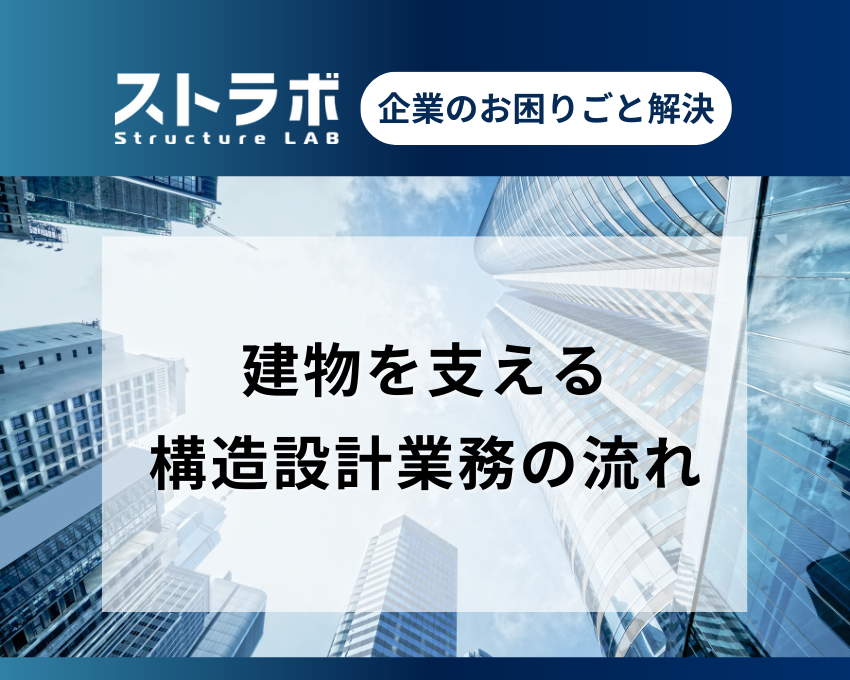
建築物を建てるには、多岐にわたる専門知識が不可欠です。現代の建築プロジェクトでは、意匠設計者、設備設計者、そして構造設計者が密に連携し、それぞれの専門性を活かして建物を完成させます。
特に構造設計は、建物の骨格を決定づける重要な領域です。居室の広さ、柱や壁の配置、建物の高さといった意匠設計の要件は、構造によって制約を受けます。
利用者が求める快適な空間と、安全性・耐震性を両立させるための最適な骨組みを設計するのが、構造設計者の使命です。本記事では、構造設計の具体的な業務の流れを順を追って解説します。
お問い合わせから基本計画提案までの初期ステップ
最初のステップは、お客様からの依頼を受けることから始まります。
電話やメールでのお問い合わせに対し、ヒアリングを通じてお客様の要望、敷地条件、予算、スケジュールといった詳細を確認します。
その後、地盤や周辺状況の既存資料を調査し、構造種別(RC造、S造など)や柱配置を想定したラフプランを提示します。意匠設計者が主体となるケースが多いですが、構造設計者はこの段階から専門的な助言を行います。
この基本計画をもとに、費用とスケジュールを提示し、契約へと進んでいきます。
- お問い合わせ:電話やメールなどで依頼を受ける
- ヒアリング:要望、敷地条件、予算、スケジュールを確認する
- 敷地調査:地盤や周辺状況を既存資料から調査する
- 基本計画提案:構造種別(RC造、S造など)や柱配置を想定したラフプランを提示。意匠設計者が主体の場合も多く、構造設計者は助言を行う
- 見積・工程提案:基本計画をもとに費用とスケジュールを提示する
契約後に進む構造設計
本契約を締結したら、プロジェクトが本格的に始動します。
社内会議やお客様とのキックオフを通じて設計方針を決定し、架構形式や荷重条件などを整理して設計ルートを設定します。この後、仮定断面の寸法を算出し、意匠や設備に影響が出る場合は迅速に調整。
地盤調査結果から最適な基礎形式(杭、フーチングなど)を選定し、構造計算を進めます。計算結果に基づいて詳細な構造図を作成し、意匠設計および設備設計とのチェックや調整を経て品質を確保します。
最終的にお客様に確認いただき、設計意図を丁寧に説明した後、すべての成果物を納品します。
- 契約:本契約を締結し、地盤調査を指示。
- 初期打合せ:社内会議とお客様とのキックオフを実施。
- 設計方針決定:架構形式、荷重条件などを整理して設計ルートを設定。
- 仮定断面:断面寸法を仮算出し、意匠や設備に影響が出る場合は迅速に調整。
- 基礎形式選定:地盤調査結果から杭やフーチングなどを決定。
- 解析・断面算定:構造計算を進め、必要に応じて計画を修正。
- 構造図作成:計算結果を基に構造設計図書を作成。
- 管理者チェック:計算書と図面の整合性、安全性を確認。
- レビュー:専門家による多角的な検証を行い、品質を高める。
- お客様確認:意匠との整合や設計意図が反映されているかをチェック。
- 計算書整理:設計方針や根拠を明記したわかりやすい計算書をまとめる。
- 設計説明:構造設計の特徴や工夫を建築主に説明。
- 納品:全体の確認を終え、成果物を納品。
申請対応から工事監理まで
納品後も構造設計者の業務は続きます。
確認申請や構造計算適合性判定に対応し、審査機関からの質疑にも回答します。
そして、最も重要なのが施工現場での工事監理です。定例会議や検査に立ち会い、設計図書通りに施工されているかを確認します。
建物の構造躯体の品質を、発注者の立場から厳しく見守ることが、建物の安全性を担保する上で不可欠です。
- 申請・判定対応:確認申請や構造計算適合性判定に対応。審査機関からの質疑にも回答。
- 現場対応・監理:定例会議や検査に立会い、施工状況を確認。構造躯体の品質を発注者の立場で見守る。
構造設計で重視すべき「コスト」と「耐震性能」
構造設計を進めるうえで最も重要なのが、コストと耐震性能の両立です。理論上は「法的に求められている耐震性を大きく上回る建物」を設計することも可能ですが、それには膨大なコストがかかり、日常の使い勝手も損なわれます。
そのため、想定される災害リスクに対して、必要十分な性能を確保しながら、コストとのバランスをとることが現実的なアプローチとなります。
特に、建物の構造種別と基礎形式は、全体のコストに大きな影響を与えます。例えば、S造はRC造と比べて柱スパンを大きく取ることが可能ですが、RC造で無理してS造と同じスパンにしようとすると柱梁が過大となり全体コストは大きく上昇します。
そのため、建物の用途や高さ、スパン、荷重条件など、多様な要因を総合的に考慮して最適な設計を導き出す必要があります。
近年では、資材や人件費の高騰を受け、プレキャストコンクリートの活用などで工期短縮や省力化を図るケースも増えています。
構造設計の品質を左右する工事監理
工事監理は、設計図書通りに施工されているかを確認し、発注者の立場で建物の品質を担保する行為です。
また、工事監理は建築士法や建築基準法で有資格者が担うべきと明確に定められた法律上の義務でもあります。
しかし、過去には構造計算書偽装事件や欠陥住宅問題など、工事監理が十分に機能していなかった事例も多数指摘されてきました。
ある研究(※)によれば、建築完了検査の実施率は2002年度の38%から2005年度には63%へと改善していますが、近年においても構造躯体や工事監理に関する事件は起こり続けています。
特に、建物の安全に直結する構造部分の施工不良は修繕が極めて困難です。
だからこそ、構造設計一級建築士のような専門知識を持つ技術者が細心の注意を払って工事監理を行うことが、建築物の安全性を左右する鍵となるのです。
<参照>
建築基準法
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/
※建築完了検査の実施率に関する研究(増渕昌利、2011)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/76/660/76_660_415/_pdf
まとめ|構造設計業務で失敗しないためのポイント
構造設計は、建物の骨格を決定づける重要な役割を担い、安全性と快適性を実現するために幅広い知識と技術が求められます。
業務の流れは、依頼から契約、設計方針の決定、構造計算や図面作成、最終的な納品まで段階的に進み、それぞれの工程で正確な判断が不可欠です。
特に、耐震性能とコストのバランスをどう取るかは設計の核心であり、構造種別や基礎形式の選定が費用と品質の両面に大きく影響します。
また、工事監理は建築基準法で義務付けられており、設計図書通りに施工されているかを確認し、施工不良を防ぐことで建物の安全性を確保します。
最終的に建築の品質を高めるには、専門知識に基づいた設計と工事監理を徹底し、技術者同士が協力して安全性と価値を守ることが不可欠です。
構造設計のスキルを伸ばしたい方やキャリアの相談をしたい方へ
ストラボでは、構造設計者向けの転職支援サービス「ストラボnavi」や、副業・独立支援の「ストラボpartner」を提供しています。
転職や副業、独立を支援するサービスを通じて、より安心できるキャリア形成をサポートします。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。