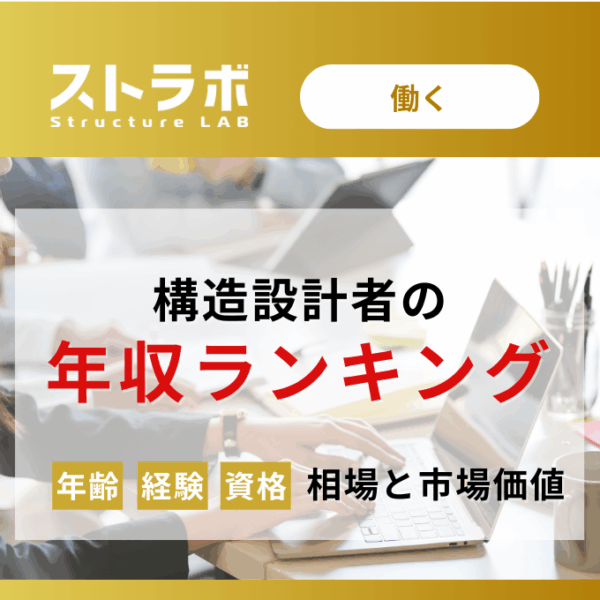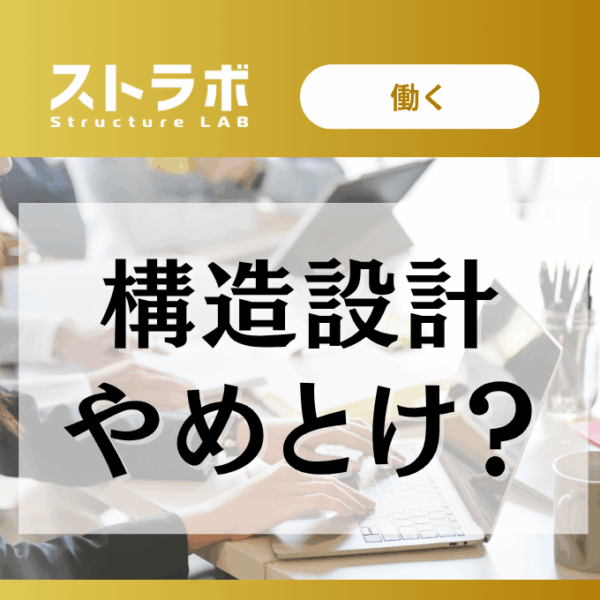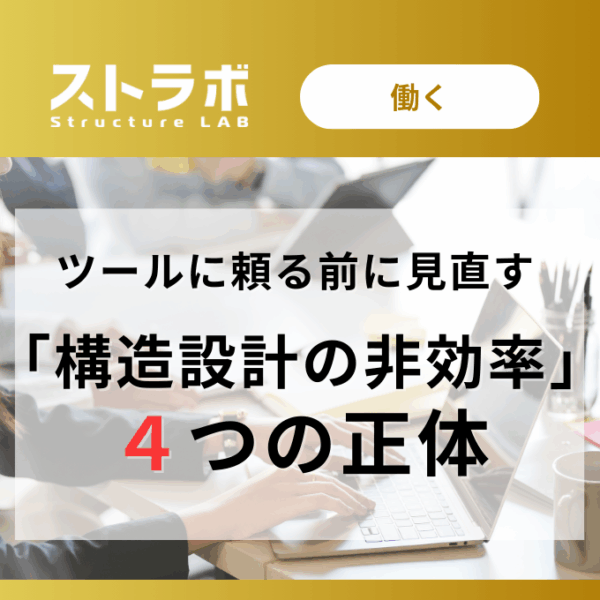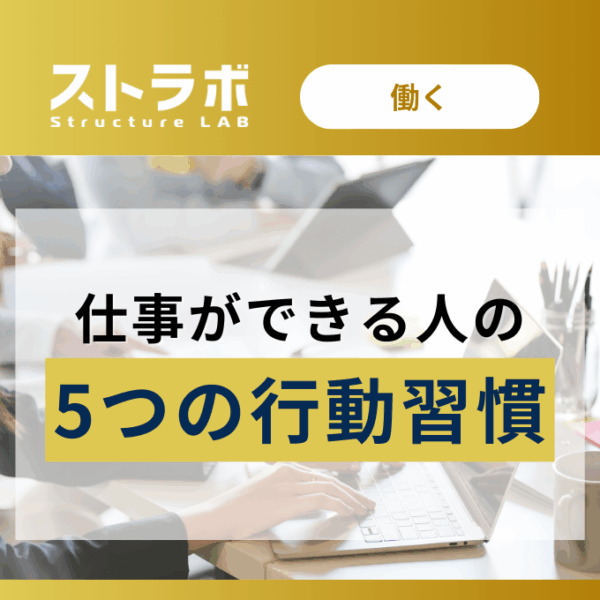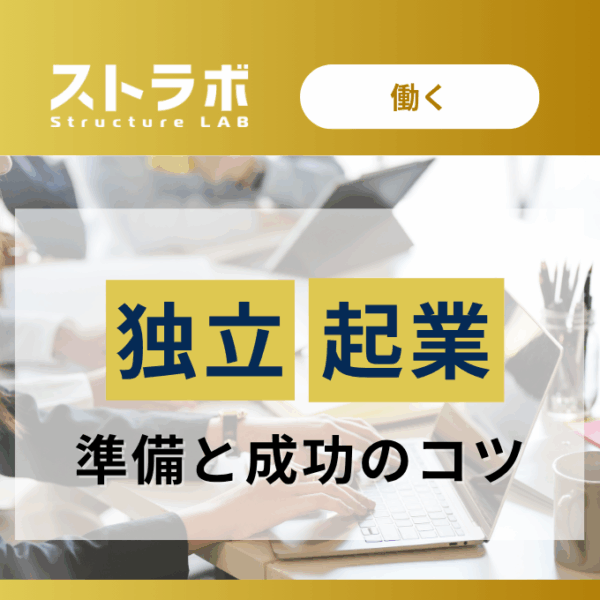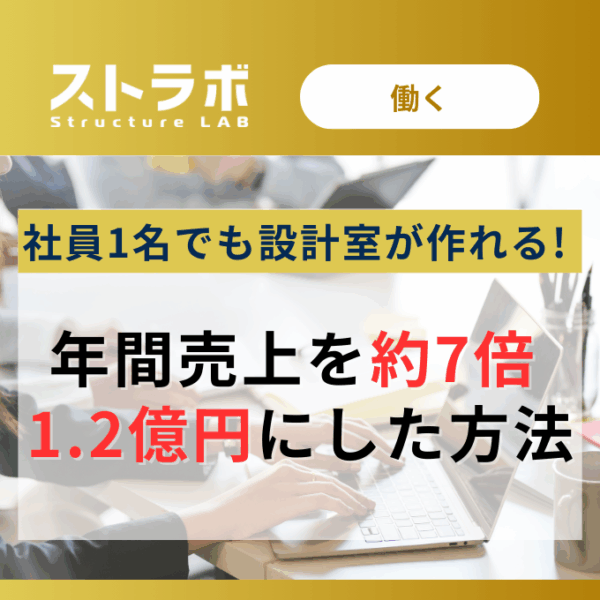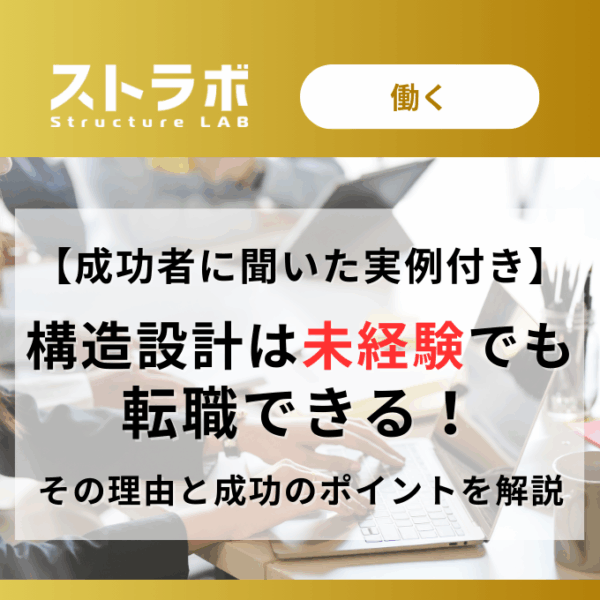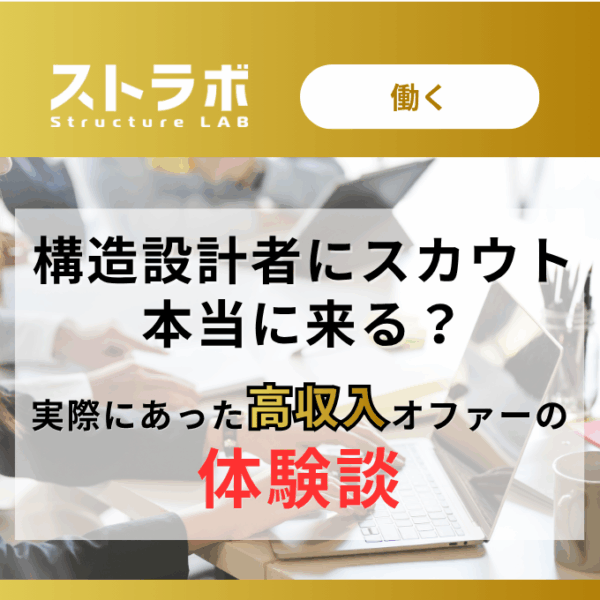建築士の転職活動は、正しく知ればノーリスクです。
転職を意識しても、最初に浮かぶのは「失敗したらどうしよう」という不安ではないでしょうか。
でも実は「転職活動を始めること」自体は、あなたが思っているほどリスクの大きい行動ではありません。
本記事では、安心して一歩を踏み出すための考え方を紹介します。
建築士の仕事で、こんな悩みを感じていませんか?
建築士として働く中で、「このまま今の環境で仕事を続けていいのだろうか」と不安を感じたことはありませんか。
責任の重さや働き方の厳しさは、多くの建築士が共通して抱える悩みです。不安を放置してしまうと将来の選択肢を狭める可能性もあります。
本節では、見過ごされがちな代表的な不満を整理し、現状を見直すきっかけにしていただければと思います。
長時間労働による負担
納期やクライアント対応を優先しすぎて生活リズムが乱れ、疲労や集中力の低下を招くことがあります。
特に変更や修正が多い案件では、予定通りに進まず夜遅くまで作業が続くこともあります。
こうした働き方が常態化すると、心身の疲れが抜けず、「この先も建築士を続けられるのか」と不安が募っていきます。
給与や待遇の不満
責任の重さに対して報酬が見合わず、深夜残業や休日対応が評価されないケースも少なくありません。
経験を積んでも給与が大きく変わらない、成果が数値で評価されにくいといった声も多いです。
努力が報われない状況が続くと、仕事への意欲が下がり、キャリアへの不安や将来への迷いにつながります。
こうした不安を抱えたまま働き続けると、選択肢を狭めてしまうこともあります。
【関連記事】
>「構造設計 やめとけ」と言われる理由とは?
>小林社長ブログ「構造設計者はやめとけ!?現役構造設計者が業界の実態を見つめ直す」
建築士の転職活動がノーリスクで始められる7つの理由
転職と聞くと「収入が下がるのでは…」「今より忙しくなるのでは…」と不安が先立ちますが、実は「転職活動」そのものに大きなリスクはありません。
むしろ、「転職活動をしない」ことのほうが、長期的にはリスクになるケースもあります。
建築業界は人材不足や制度改正など、変化のスピードが年々上がっています。
何もしないまま数年が過ぎてしまうと、気づかぬうちに市場価値が下がり、キャリアアップの機会を逃してしまうことも……
だからこそ、「何もしないことでキャリアアップのチャンスを逃すリスク」を意識しながら転職活動を進めることが大切です。
転職活動は、あなたのキャリアを守るための「準備」。
安心して一歩を踏み出せるように転職活動がノーリスクである理由を7つ紹介します。
1. お金のリスクはゼロ
転職活動は実は一切お金がかかりません。
求人サイトへの登録はもちろん、キャリアアドバイザーとの面談や選考サポート、内定に至るまで、求職者はすべて無料でサービスを利用できます。
実際に「まずは登録だけして、求人情報をパッと見てみる」という人も非常に多いのは、この金銭的な安心感があるからです。
「金銭的な負担がない」からこそ、気軽に動けるのが大きなメリットです。
2. 現職を続けながら活動できる
仕事を辞めずに転職活動を進められるのは、何よりも大きな安心材料ですよね。
収入や生活を維持したまま準備を進められるので、たとえ選考が思うように進まなくても、生活に金銭的な大きなダメージはありません。
- キャリアアドバイザーとの面談:「平日の夜や土日」など、柔軟に対応してくれる転職エージェントが増えています。
- 企業との面接:最近はオンライン面接が一般的になり、有給を取らずに済むケースも増えました。休憩時間や終業後など、時間の調整がしやすくなっています。
3. 内定が出ても、条件が合わなければ断ってOK
転職活動は、あなた自身が職場を選ぶための行動です。
仮に内定が出たとしても、「提示された年収が希望より低い」「勤務地が変わってしまいそう」など、条件がイマイチと感じたら、遠慮なく辞退して大丈夫です。
入社を強制されることはありませんので安心してください。
さらに、複数の内定を比較検討することで、「自分にとって本当に良い職場」を冷静に見極めることができます。
比較検討の機会を得られること自体が、転職活動の大きな価値です。
4. 現職にバレる心配は、ほぼしなくていい
「今の会社に転職活動を知られたらどうしよう」と心配になるかもしれませんが、個人情報が漏れるケースは極めて稀です。
【転職活動していることが現職にバレない理由】
- エージェントの秘密保持:転職エージェントは、個人情報を厳重に管理しています。
- ブロック機能の活用:求人サイトやエージェントには、「現職の会社や関係先をブロック」できる設定があり、情報が届くのを防げます。
- オンライン面談の普及:休日や就業後の時間を指定し、オンラインで完結できるため、同僚に気づかれる心配もほとんどありません。
5.いざというときに備えられる
転職活動を進めておくこと自体が、将来への大きな備えになります。
責任感の強い建築士ほど、「もう本当に限界だ!」と突然燃え尽きてしまうことがあります。
そんな精神的な危機が訪れたときでも、すでに情報収集や企業への応募準備ができていれば、焦らず、落ち着いて次の行動が取れます。
安心できる「逃げ道」を用意しておくことで、日々の仕事にも少し余裕を持てるようになるはずです。
6. 比較することで現職の良さに気付ける
他社の求人をじっくり見てみると、「あれ、うちの会社って案外悪くないかも?」と、現職の良さにハッと気づくこともあります。
「残業時間は多いけど、給与水準は業界内ではトップクラスなんだ」
「人間関係は面倒だけど、大規模案件に携われるのはうちだけだ」
待遇や働き方、人間関係など、他社と比較するからこそ「今の環境の強み」が客観的に見えてくるんです。
比較した結果、今の会社の方が自分に合っていると感じられれば、無理に転職する必要はありません。
「今の職場を続けるのも悪くない」と納得して選択できることも、転職活動の大きな価値なんです。
7. 市場価値を客観的に把握できる
転職活動を進めることは、自分の市場価値を客観的に知る、またとないチャンスです。
提示される年収水準や面接での評価は、企業があなたの経験を正当に評価した結果です。
「自分はRC造やS造の設計経験が強みとして評価されている」
「逆にマネジメント経験や最新ソフトの活用スキルが足りていない」
このように現状を整理できれば、今後の学びや資格取得の方向性など、「これから何を学ぶべきか」の指針が定まります。
実際に転職しなくても、自分の立ち位置を把握できるだけで大きな収穫になります。
建築士の転職リスクと対策
転職活動自体は安全ですが、入社後に「思っていたのと違う」と後悔しないために、建築業界特有のリスクと対策を事前に把握しておくことが重要です。
本節では、建築士が直面しやすい4つのリアルなリスクを簡潔に整理します。
リスク1:年収が下がる
事務所規模や案件単価により、報酬水準が大幅に下がるケースがあります。
低賃金のまま激務になるリスクがあるため、事前の確認は不可欠です。
【対策】
面接で、等級・評価基準、昇給ペース、そして固定残業代の超過分の扱いについて、深掘りして確認しましょう。
リスク2:働き方が変わらない
求人票の平均残業時間と実態が異なるケースは珍しくありません。
人材不足の業界では、求人情報だけでは実際の残業や体制が分かりづらいのが実情です。
【対策】
「逆質問」で現場の状況を具体的に聞き出すことが重要です。
「配属予定チームの案件数」「繁忙期の実残業時間」などを尋ねましょう。
リスク3:人材不足で即戦力として酷使される
「教育体制バッチリ」とあっても、実際は人手不足から入社直後から大量の案件を抱えることがあります。
中小企業やベンチャー企業に多く「即戦力として酷使された」と感じるケースも聞かれます。
【対策】
「入社後のOJT研修や引継ぎ計画」「増員計画の有無」など、フォロー体制や将来計画を聞くことで、組織体制への投資意欲を測れます。
リスク4:キャリアの一貫性が失われる
転職を重ねて専門軸がぼやけると、「何でも屋」になり、将来的な選択肢を狭めるリスクがあります。
特に30代後半以降は、自身の専門家としての明確な軸を持つことが不可欠です。
【対策】
得意な建物用途・構造種別・担当範囲の“軸”を明確に定義し、それに合致する求人を狙うようにしましょう。
軸があれば、経験を「武器」として活かせます。
「思っていたのと違う!」を防ぐ、建築士事務所選びの注意点
建築士が転職を考える際は、一般的なリスクに加えて建築業界の常識を知ることが欠かせません。事務所のタイプや職種によって、働き方やキャリア形成のルートは大きく異なります。
建築設計事務所の働き方と注意点
建築設計事務所や、職場ごとの働き方と注意点は下記のとおりです。
|
事務所タイプ |
求められる役割と働き方 |
注意点 |
|
ゼネコン設計部 |
大規模案件に携わる。キャリアの安定感は抜群。 |
施工部門や外部のアウトソーシング部分との調整業務が多くで、裁量は限定されがち。「設計にかける時間より他者との調整にかかる時間が多くなりマネジメント業 」になることも。 |
|
組織設計事務所 |
大規模案件に携わる。給与水準は高め。 |
分業が徹底されており、担当範囲が狭く「全体像が見えない」と悩む人もいる。また配置転換とキャリアプランに一貫性が無い場合は技術力が虫食い状態になることも |
|
アトリエ系設計事務所 |
デザイン性の高い案件に挑戦できる。 |
独自性が求められ、一般的に量産される建築の枠外での意匠と設備構造の調和を求められるため案件1つにかかる時間が長くなりやすい。また、建築家としてのブランディングによりデザイン面や得意分野での仕事の方向性が絞られる傾向があり多方面での経験値を積みにくい場合がある。。 |
|
中小設計事務所 |
業務全体を幅広く経験できる。 |
人手不足で一人の負担や作業範囲が非常に大きい。(人員不足により業務分担が難しく大量の業務を抱えることにより激務化リスクも。)教育体制が未整備なことも多い。 |
職種(意匠・構造・設備)別の注意点
意匠設計・構造設計・設備設計ごとの注意点は下記のとおりです。
|
職種 |
注意点 |
|
意匠設計 |
施主調整やそもそもの業務範囲が広く、特に納期前の長時間労働に陥りやすい。自社商品が定型化されているとデザインの自由度が低い職場もある。 |
|
構造設計 |
求人が少なく小規模事務所が多いため選択肢が限られる。重い責任に対して待遇改善が遅れているケースもあるが、近年は改善傾向も見られる。 |
|
設備設計 |
需要は高いが人材不足で業務が広がりがち。一人前になるまでの経験年数が多く必要なため教育体制が不十分だと「OJTもなく丸投げされた」という辛い経験をする人も。 |
面接・公式HP・求人票チェック術
転職で失敗しないためには、求人票の条件だけでなく、公式HPや面接などから得られる情報を総合的に見極めることが欠かせません。
求人票は『会社の顔』にすぎません。
「うちの会社は良いですよ!」という情報しか書いてありませんから、鵜呑みにするのは危険です。
本節では、「思っていた環境と違った」と後悔しないために、転職前に確認しておきたい3ステップを整理しました。
ステップ1:求人票から「企業の体質」を見極める
まず注目したいのは 「残業時間」「離職率」「案件数・案件規模」 の3つです。
残業時間と固定残業代
「月20時間分の固定残業代を含む」と記載がある場合、「超過分の扱いが明確に規定されているか」を必ず確認しておくことが重要です。
ここが曖昧な会社は、入社後にサービス残業を強いられるリスクが高いと判断できます。
離職率の推測
離職率が明記されていなくても、「平均勤続年数」や「社員数の推移」をチェックすることで、社員の定着率を間接的に推測できます。
平均勤続年数が異常に短い場合は、注意が必要です。
案件数・案件規模
案件数が異常に多いのに社員数が少ない、あるいは担当する建築物の規模があなたの希望と合っているかなど、「設計者としての裁量」に関わる大切な指標を確認しましょう。
ステップ2:公式HPで会社の「価値観」を読み解く
求人票だけではわからない「会社の雰囲気」や「価値観」は、公式HPが最も参考になります。
社員インタビュー
社員インタビューを読み、「どんな働き方を大切にしているのか」「どんな人が活躍しているのか」を具体的に読み解きましょう。
「プライベートも充実している」という声が多いか、「仕事への情熱一筋」という声が多いかで、「社風の傾向」が見えてきます。
教育体制・福利厚生
教育体制・福利厚生・キャリア支援制度について「情報がほとんど載っていない」場合は、社員の成長や定着に対する意識が低い可能性があります。
逆に、詳細に記載されている会社は、社員を大切にしている傾向があると判断できます。
経営者のメッセージ
経営者が何を語っているかを見ることで、会社の「長期的なビジョン」を把握できます。
ビジョンに共感できるかどうかは、長く働く上で非常に重要です。
ステップ3:面接での「逆質問」で現場のリアルを聞き出す
|
逆質問 |
読み解けるリアルな情報 |
|
「設計の担当範囲はどこまでですか?」 |
業務の裁量範囲、最新技術への対応度 |
|
「配属チームは今、何件の案件を抱えていますか?」 |
現場の忙しさ、人員不足の深刻度 |
|
「長く働いている社員の特徴や、定着している理由は何ですか?」 |
会社が大切にしている人物像、職場の満足度 |
|
「入社1年後、私にはどのような役割を期待していますか?」 |
育成への本気度、キャリアパスの明確さ |
面接の最後に用意される「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、「職場のリアルを見抜く絶好のチャンス」です。
逆質問は「この会社に興味がある!」という熱意を伝える場でもあり、面接官の印象アップにもつながります。
漠然とした質問ではなく、上記のような「具体的で踏み込んだ質問」をすることで、相手の回答の曖昧さからも、会社の体質を見抜くことができます。
資格別(一級建築士/二級建築士/構造設計一級建築士)転職の可能性と注意点
建築士の資格は、転職市場での評価やキャリアの広がり方に大きな影響を与えます。
特に一級建築士は、そのステータスの高さから、転職によって待遇を改善しやすい傾向にあります。
一級建築士なら|大規模案件やマネジメントでキャリアアップ
一級建築士は、建築士の中で最も幅広い業務を担える「最強の国家資格」です。
特に大規模案件やマネジメント領域で強みを発揮します。
大規模案件に携われるチャンス
公共施設や大型マンション、商業施設といった、社会的にインパクトの大きいプロジェクトに関われる可能性が大きく広がります。
マネジメント職に抜擢されやすい
資格を持つことで信頼性が高まり、プロジェクトリーダーや設計部門の責任者といった「マネジメントポジション」に就きやすくなります。
年収アップの可能性が高い
二級建築士に比べて待遇面で優遇される傾向があり、「資格手当」や「役職手当」を設定している企業も多いです。
転職によって年収アップにつながるケースも多いでしょう。
二級建築士なら|地域密着や中小事務所で安定した働き方
二級建築士は住宅や小規模案件に強みを持ち、地域密着型の働き方に適しています。
地域に根ざした案件に強い
戸建住宅やリフォーム需要が中心のため、地域社会に貢献できる実感を持ちやすいのが特徴です。
特に中小設計事務所では需要が安定しています。
幅広い業務経験を積める
中小設計事務所では基本計画から工事監理まで「一連の業務を幅広く担当できる」ことが多く、実務スキルを磨けます。
将来、一級建築士を目指す際にも大きな財産になります。
ワークライフバランスが取りやすい
大規模案件を抱えるゼネコンに比べ、生活との両立を重視した働き方を選びやすいのもメリットです。
構造設計一級建築士なら|専門性を武器に高年収・大規模案件へ
構造設計一級建築士は、建築分野でも特に専門性が高く評価される希少価値の高い資格です。
高い専門性が評価される
耐震性や安全性を担保する構造設計は、建物の根幹を支える仕事です。
高度な専門スキルを持つことで、求人企業からの引き合いも強くなります。
キャリアの希少価値がある
保有者は約1万名と非常に少なく一級建築士の中でも数%程度の希少性です。
一定規模以上の建築物では構造設計専任が義務付けられるため、市場価値が極めて高いです。
企業にとって採用競争が激しい職種であり、転職活動でも優位に立ちやすいという特徴があります。
年収水準が高い
専門性の高さから転職市場でも高い待遇が期待できます。
実際に年収1,000万円を超える求人も存在しており、希少性と専門性を武器にすれば、一般的な建築技術者と比べてもワンランク上の待遇を狙えます。
<参考>
日本建築技術教育普及センター
www.jaeic.or.jp/other_info/index.files/jaeic_pamplet202504.pdf
資格がない場合・未経験から目指す場合
資格を持たない場合や未経験から目指す場合でも、実務経験や熱意を武器にすれば、チャンスは十分にあります。
実務経験が強みになる
資格がなくても、設計チームの一員として図面作成や設計の一部を担当できるケースはあります。
実務経験を積みながら働くこと自体が評価につながります。
未経験者はアシスタントから
未経験者は、設計補助や図面作成サポートといった業務からスタートするのが一般的です。
基礎を学びながら実務感覚を養うことができ、将来的なキャリアの土台になります。
資格取得支援制度を活用
働きながら二級建築士や一級建築士を目指すルートを選びましょう。
企業によっては「資格取得支援制度」を持つところもあるため、そうした環境を選ぶのは一つの戦略です。
「もう辞めたい」と思ったら、まずは焦らず情報収集から始めよう
「今の環境を変えたい」と感じる建築士は多いものの、焦って辞めてしまうと「こんなはずじゃなかった…」と後悔につながることもあります。
転職活動を始めること自体は、将来への「備え」になります。
むしろ、何もせずに今の環境に留まり続けるほうが、キャリアアップのチャンスを逃してしまう可能性があります。
情報を集めて自分の市場価値を知ることが、将来の安心につながる第一歩です。
とはいえ、自分一人で情報を集めるには限界があり、求人票だけでは職場の実態までは見抜けません。
そんなときこそ、構造設計者に特化した転職支援サービスで、構造設計業界を熟知したプロに相談してみませんか?
「ストラボnavi」なら、完全無料で利用でき、今の職場に転職活動が知られる心配もありません。
業界を熟知したキャリアアドバイザーが、「求人票に載らない社風・残業実態・キャリアパス」まで丁寧に確認し、あなたの不安を解消してくれます。
技術力や志向を正確に見極めたうえで最適な企業を紹介するため、「入社後にイメージと違った」というリスクを防げるのが最大の強みです。
さらに、意匠設計や設備設計から構造設計へのキャリア転向を希望する方にも対応しており、専門性を高めたい方にとって大きなチャンスとなるはずです。
転職を「決める」前に、まずは情報を知ることから。
キャリアの可能性を広げる第一歩として、気軽にチェックしてみてください。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。