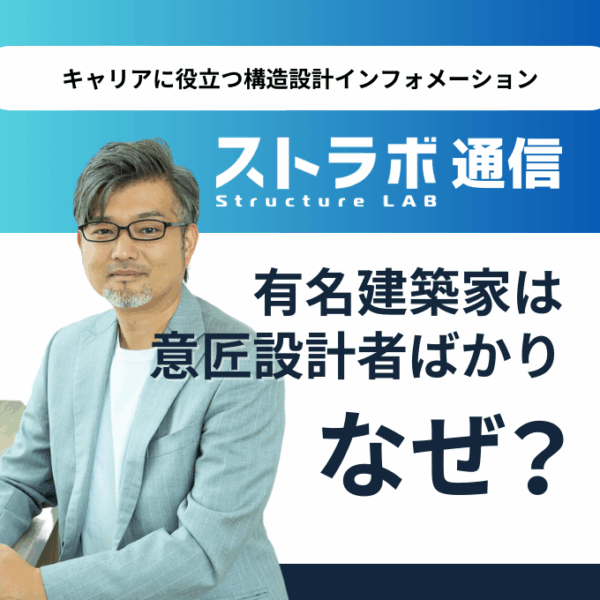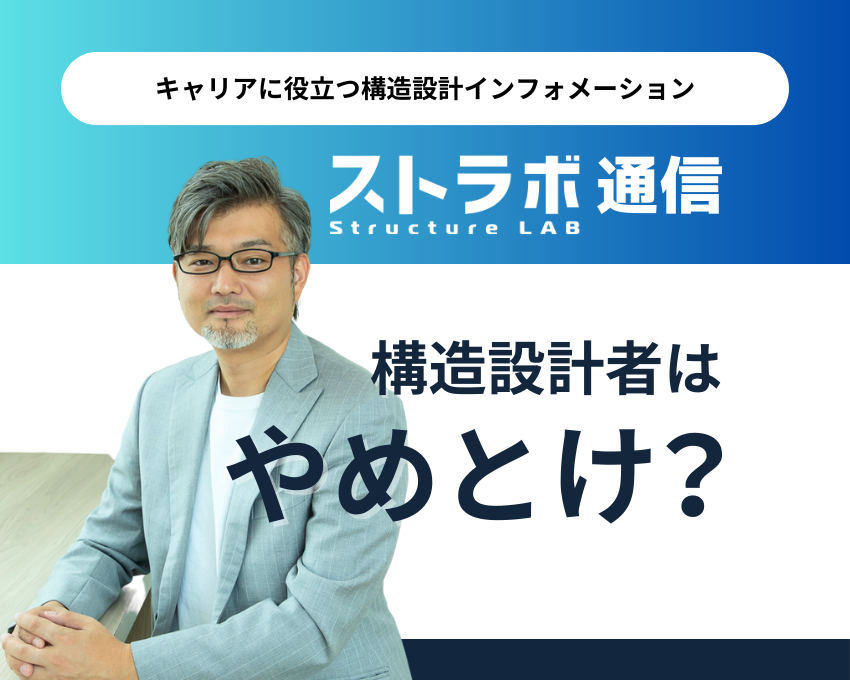
こんにちは!現役の構造設計者であり、株式会社ストラボ代表の小林です。
今回の「ストラボ通信」では、少し踏み込んだテーマ「構造設計は“やめとけ”?」について、皆さんと考えていきたいと思います。
Googleなどで「構造設計」と検索した時、「構造設計 やめとけ」という検索候補を見たことがある人は多いのではないでしょうか。自分が誇りを持っている職業が、ネガティブな言葉で語られるのは、正直残念な気持ちになります。
しかし、そう言われてしまう原因に、私自身も心当たりがないわけではありません。
今回は、この検索ワードに込められた想いや、私なりの考えを本音でお話ししたいと思います。
「構造設計者 やめとけ」と検索される背景にあるもの
この「やめとけ」という言葉は、きっと先輩エンジニアたちの心からの叫びなのだと思います。
検索候補になってしまうほど、構造設計者として働き続ける未来にネガティブな感情を抱く人が多いということなのでしょう。たしかに、構造設計者を取り巻く労働環境の改善は、思うように進んでいないと感じる場面は今でもあります。
また、構造設計業界は、小規模な事務所が圧倒的に多いという特徴があります。そのため、仕事をしていく上で、同じ苦労を分かち合える同期や同年代の意見を聞く機会が少ないのが現状です。常に孤独を感じ、年の近い先輩に気軽にアドバイスを求めたり、日々のつらさを吐き出したりする場がない。
もちろん、専門的で責任の重い業務内容も原因の一つですが、こうした業界・職種特有の「孤独な環境」こそが、この検索ワードの背景にあるのかもしれません。
20年以上、構造設計者として働いてきた先人の一人として、こうした労働環境を改善できなかった責任を、私自身も感じています。
私が考える、それでも構造設計者を目指すべき理由
「構造設計者 やめとけ」の検索結果で表示されるWebページに書かれていることが、全くの嘘だとは思いません。
しかし、どうか少しだけ、私に名誉挽回の機会をください。
構造設計者を目指したい、続けていきたいと思えるような、ポジティブな理由をいくつかご紹介します。
- 設計現場で使う数学知識は、実は中学レベルで十分
- 「手に職」だから、独立という選択肢を選びやすい
- 業界全体が人手不足で、志望者が歓迎される「穴場」な状況
平面図から立体を想像する力など、向き不向きはあります。しかし、現場で使用する数式は難しそうに見えても、何が結果に影響するかを理解することが重要で、中学レベルの数学が苦手でなければ実務は問題ないと言えます。
さらに、スキルを磨けば高収入や独立を目指しやすい。構造設計業界に小規模事務所が多いのは、これが理由です。会社に依存しない自由な生き方ができるという意味で、かなり大きなメリットなのではないでしょうか。
もちろん、「構造設計者 やめとけ」と言われるように、単純作業が多いことや、意匠設計との調整が難しいなど、どうしても避けられない「業務のつらさ」はあります。
ただそれ以上に、クリエイティブな面白さや、人命を守るという大きなやりがいがあることを、私はもっと広く発信していきたいと考えています。
ストラボが構造設計者の「孤独」を解決する
今回は、構造設計業界ならではの「孤独な労働環境」についても少し触れました。
私は、小規模事務所がほとんどを占める構造設計業界だからこそ、孤独を感じているエンジニア同士がつながる場が必要だと考え、ストラボを創りました。
ストラボが目指すのは、ただの転職サイトや情報サイトではありません。「構造設計という専門的な分野でエンジニアが成長し、社会的価値を高められる場」となることです。既存の仕組みを超え、構造設計者が社会でより力を発揮できるような、新しい機会と価値を提供していきたいと考えています。
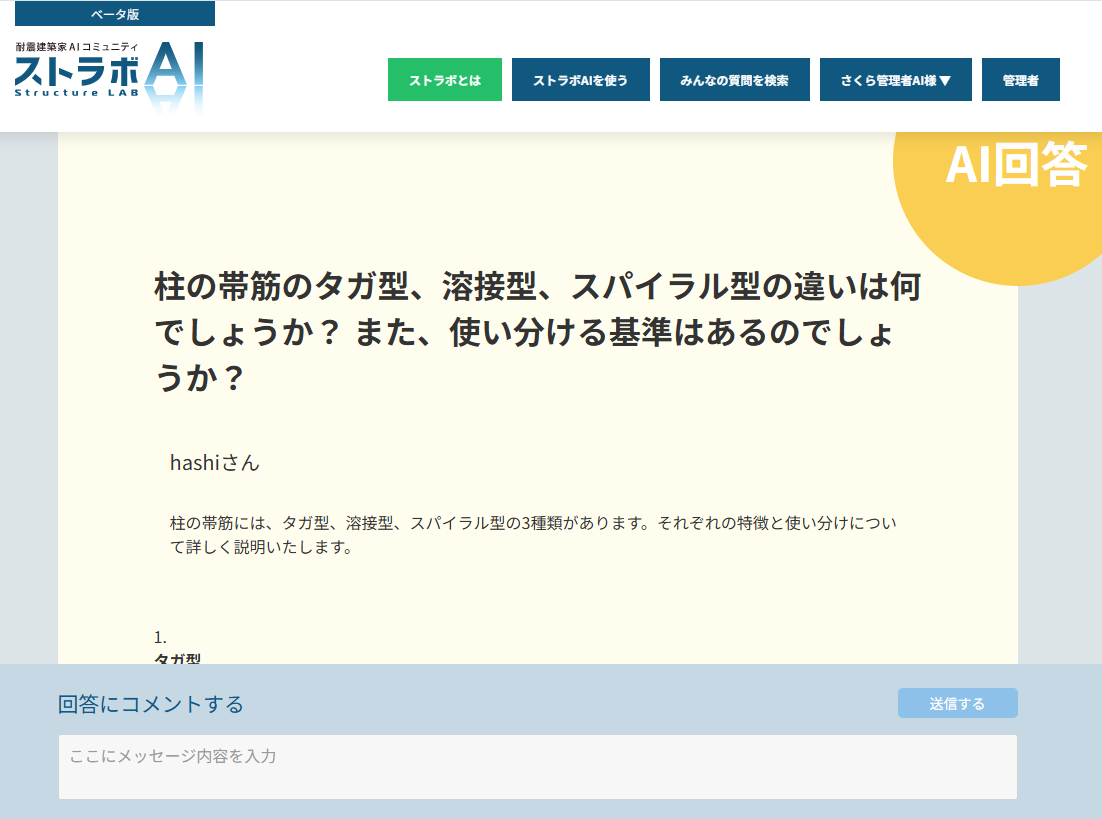
その第一歩として、構造設計者同士のコミュニケーションツールになってほしいという願いを込めて開発したのが、AI型 Q&Aコミュニティ「ストラボAI」です。
建築構造についての疑問にAIが回答してくれるだけでなく、構造設計者の他ユーザーが書き込める掲示板機能を備えています。
職場に気軽に相談できる先輩や上司がいなくても、「ストラボAI」を通じてアドバイスを送り合い、日々励まし合う場として活用されることを期待しています。
今後も「ストラボ通信」では、構造設計者の現状分析や特有の悩みなど、構造設計に関する様々な情報を発信していきます。またお会いしましょう!
執筆者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。
関連記事一覧
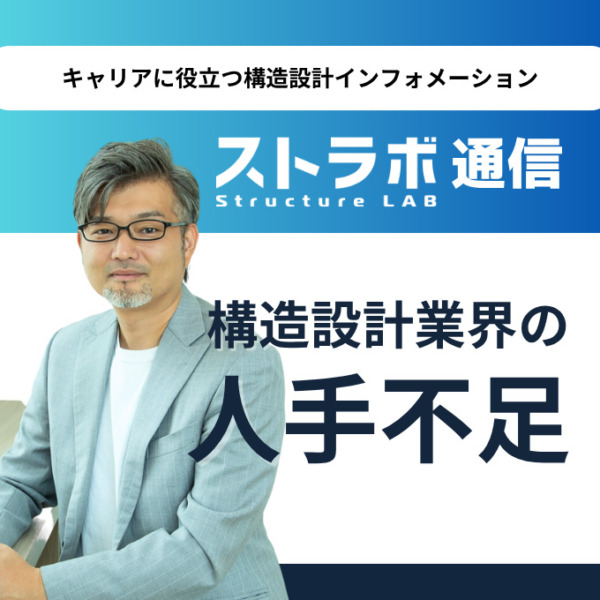
人手不足を逆手に取る!構造設計者だからこそのキャリアアップ戦略

【独立したい人必見】構造設計で月額報酬+ボーナスの安定収入を実現する方法

構造設計の研修は「経済設計」に役立たない?1万件のノウハウを活用した新しい教育...
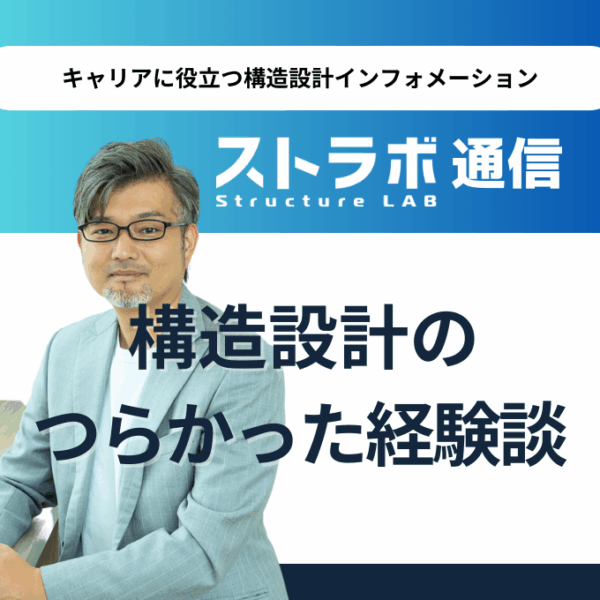
「2週間徹夜した」構造設計のツラかった体験!構造設計の悩みをAIで瞬時に解決

【ユーザーの声紹介】人手不足を解消し働き方を柔軟にするマッチングサービス|ス...
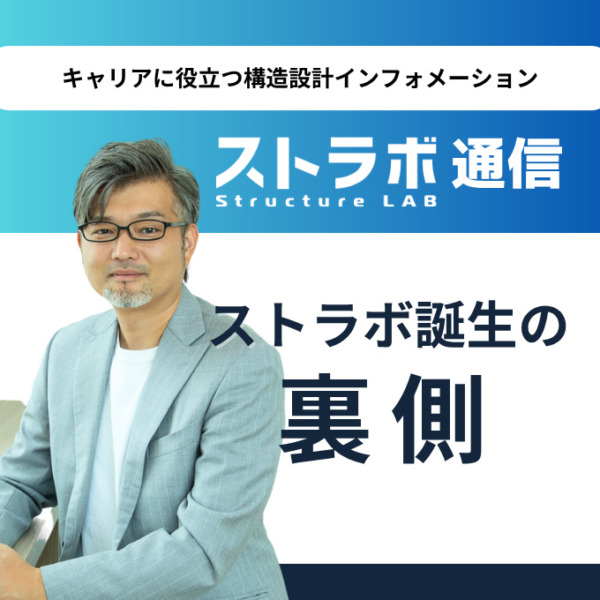
新サービス誕生の裏側|構造設計業界の壁を越える新しい挑戦と目指す未来
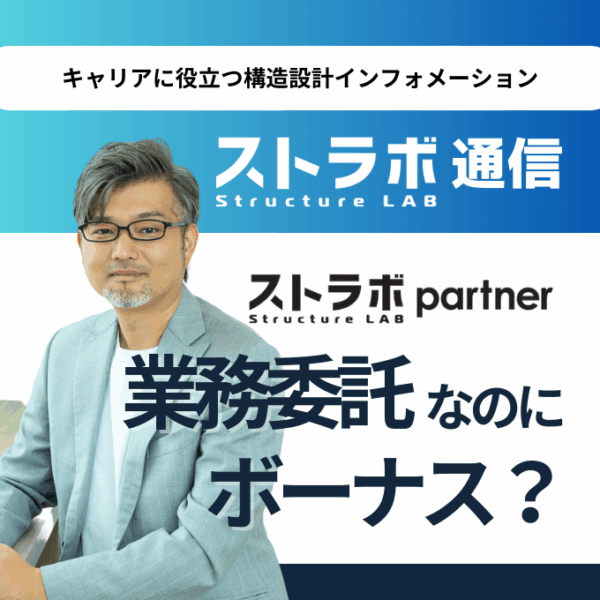
業務委託なのにボーナスあり!副業・独立後に安定収入を即確保|ストラボpartner