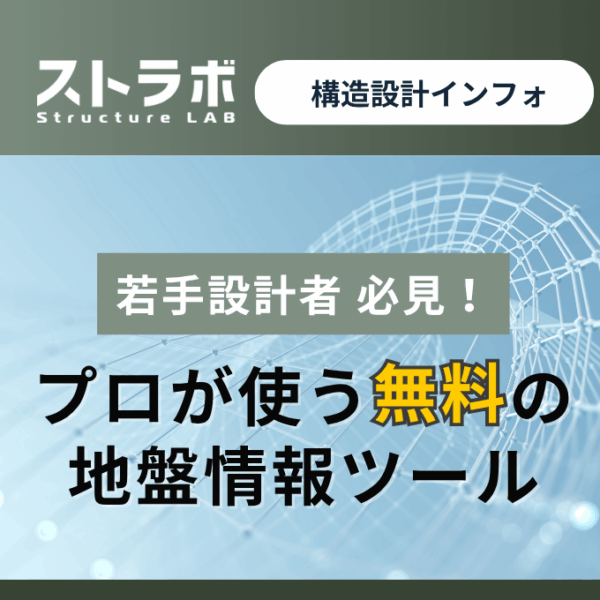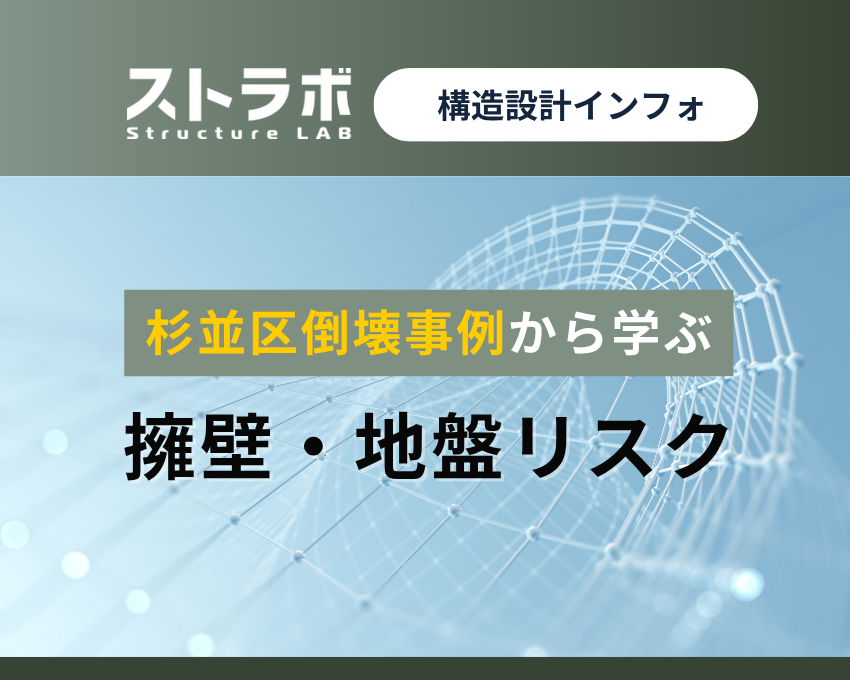
杉並区で擁壁が崩れ住宅が倒壊したニュースが全国で報じられています。構造設計業界にも強い衝撃を与えました。建物が健全でも、擁壁・地盤・排水が崩れれば暮らしの安全は守れません。
杉並区擁壁崩壊から構造設計の責任を再考する
2025年9月30日夜、東京都杉並区堀ノ内で高さ4〜5mの擁壁が崩れ、木造2階建て住宅が全壊しました。
幸い人的被害は確認されていませんが、杉並区は周辺世帯に避難を促し、原因調査を進めています。
擁壁の維持管理や地盤排水の重要性が改めて突きつけられました。現地では「以前からひび割れや漏水があった」との証言も報じられています。
【目撃証言】#注意喚起 東京都中野区 杉並区堀ノ内 方南町駅付近 家屋の倒壊事故発生 消防多数出動事案9月30日 #中野 #杉並区 #方南町 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/YdvKLN7o4J #NHK #杉並区 #中野区 消防車サイレン空き家当該古い家 pic.twitter.com/PhvQV91UE4
— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) September 30, 2025
「建物本体は無事でも、足元(地盤・擁壁)が崩れる」リスクは、特に高低差のある敷地では常に存在します。
本記事では、この社会事象を例に、技術的な擁壁・地盤リスクを整理します。そして現場で不可欠なチェックポイントを解説します。
<参照>
杉並区役所【第1報】堀ノ内一丁目の家屋倒壊について
https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/23240.html
直前に「大きな音」住民証言 住宅倒壊前後の映像など入手 東京・杉並区
https://news.ntv.co.jp/category/society/dbfd8e387f2742e2baab8e45284a1b5
なぜ「擁壁・地盤」が先に崩れるのか?二段擁壁・排水不良・上載荷重
今回の倒壊は、建物の上部構造の耐力不足というより、擁壁区画の土砂崩壊的挙動が先行し、建物が巻き込まれた可能性が指摘されています。
報道からは、擁壁のひび割れや漏水があったこと、また高低差のある敷地で擁壁上に1階がのるような配置だったことがわかっています。
杉並区堀ノ内1丁目 住宅崩壊 擁壁亀裂
いつか崩れると思ったので、今年の3月に写真撮影。9月末本当に崩れて、正面のプラウドに瓦礫なだれ込み。
プラウドは6500万円位から売りに出されていて、日の当たらない東向きの現場側は全て入居済。
近くに4LDK新築一戸建7000万で物件あったのに。 pic.twitter.com/u6L6LL8PuB— ゆんける (@kouhdfxdl) October 2, 2025
擁壁の損傷・排水機能低下・背面土の飽和・地震・降雨などの複合的な要因により、受動土圧の低下や滑動・転倒が生じうる典型的な例です。
また、自治体の「がけ条例」では、崖や擁壁からの距離を一定以上離すこと、あるいは、構造的に安全な擁壁や遮蔽壁、RC外壁を設けることで、建物の安全性を確保する考え方が示されています。
建物を計画する際は、まず『がけ条例』や擁壁の条件をしっかり確認し、それを踏まえた配置にしなければなりません。
特に、深基礎や杭といった基礎形式の選定、そして擁壁の適法性や性能の確認は、絶対に欠かせない作業です。
<参照>千葉県 建築基準法施行条例第4条(がけ条例)について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/houritsu/gake.html
構造設計実務における擁壁設計のチェックリスト
構造設計実務において、既存擁壁や敷地造成を伴う建築計画で確認すべき最重要項目を整理します。
1)適法性・証憑(検査済証の有無)
- 高さ・種別: 2m超(地域により3m超)の擁壁は、対象法令・基準に適合した構造と証憑(検査済証・確認図書等)が必要です。
- 既存擁壁の注意点: 不適格擁壁(検査済証なし、旧基準、大谷石・空石積み等)がないか徹底的にチェックします。
2)二重擁壁(二段擁壁)の危険性
- 二重擁壁(二段擁壁): 既存擁壁の上にブロック等を重ねた二重擁壁(二段擁壁)は、宅地造成等規制法上の違反となる場合があります。
地震時は倒壊リスクが高く、実際にブロック塀の倒壊で死亡事故が発生し、民事訴訟に発展した例もあります。※
3)地盤・土圧・排水機能
- 排水機能(水抜き穴・裏込め): 背面土の粒度・透水性、湧水の有無を把握し、排水機能の健全性を確認します。ひび割れや滞水は危険サインです。
- 設計土圧: 常時/地震時土圧、背面勾配、上載荷重(車両・建築物)、フェンス等の付加荷重を適切に反映します。
4)安定性の検討
- 滑動・転倒・地耐力: 安定余裕の確保、基礎地盤支持力、すべり円弧(全体安定)を検討します。控え長・フーチング寸法は計算値に裏付けが必要です。
5)がけ条例との整合
- がけ条例対応: 30°ライン/2H規制の考え方を押さえ、離隔・深基礎・杭打設等の組み合わせで安全性を確保します。
6)劣化兆候と維持管理
- 劣化兆候の把握: クラック、エフロ(白華)、天端の欠損、鉛直/水平変位、排水不良を確認します。
- 管理の標準化: 「写真記録→定期点検→補修計画」の運用を標準化します。報道の「漏水・ひび」は典型的な警戒サインです。
7)建築計画との接続と責任
- 配置計画: 擁壁上に主要構造を載せる計画は、深基礎/杭・独立した土留め等で荷重分担を整理し、敷地造成と建築の設計責任の接続を明確化します。
- 確認申請と審査: 2025年改正で木造2階建ては「新2号建築物」となり、いわゆる審査省略の対象から外れます。これにより確認申請では構造関係図書の提出と審査が必須となり、結果として擁壁やがけなど敷地条件に起因する安全性も、従来より指摘・補正の対象になりやすくなります。
<参照>※ブロック塀倒壊、熊本地震の死亡事故では6700万円の賠償請求も
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00169/
構造設計者が経験した擁壁・地盤リスクのヒヤリハット事例
構造設計実務で発生した具体的なヒヤリハット事例から、初期段階のチェックの重要性を学びます。
- 二重擁壁を“現況優先”で見逃し→建替え期に全面やり直し
境界上に継ぎ足しブロックが見つかり、造成認定や検査済証がなし。建替え確認で宅造適合の新設擁壁が必須となり、数百万円規模の追加費用に。初期調査での証憑確認の甘さがボトルネックに。 - がけ条例の離隔不足→深基礎+杭に設計変更
30°ライン内に主要構造がかかるため、深基礎・杭で安息角以深まで抵抗要素を確保して適合化。構造・コスト・工程に影響するため、計画初期の条例確認が肝。 - 背面排水詰まり→豪雨で一気に土圧上昇
水抜き穴の目詰まりと背面土の細粒分増加で飽和。豪雨後に天端の水平変位・クラック進行。「水がチョロチョロ」は、この前兆に重なる。定期点検と排水補修が重要。
<参照>擁壁(ようへき)~基本知識とトラブル
https://fr-plus.jp/usefulread/step2/hard1-12
FAQ
Q1. 二段擁壁(二重擁壁)はなぜ危険・違法になり得るのですか?
- 既存の擁壁の上にブロックなどを継ぎ足すと、土からの圧力(背面土圧)や地震の際に加わる力(水平力)の流れが不連続になってしまいます。
その結果、擁壁が滑ったり倒れたり(滑動・転倒)、地盤全体が不安定になったりするリスクが高くなります。
また、こうした継ぎ足しは、本来必要な造成許可や確認申請、検査済証の要件を満たさないケースが多く、宅地造成等規制法や各自治体の基準に抵触する違法状態になる可能性があります。
安全確保と法令順守の観点から、二重擁壁は原則としてやり直し(新設)で評価するのが実務上の対応です。
Q2. がけ条例の「30°ライン/2H」とは何ですか?離隔できない場合の設計代替案はありますか?
- これは、崖や擁壁の天端(てんば:一番上の端)から、特定の傾斜(30°)または高低差(H)の水平距離(2H)の範囲を危険区域とみなし、建物の主要構造部をその区域から遠ざけるという考え方です。
もしこの離隔が難しい場合は、以下の設計で安全性を確保します(事前に所管行政庁との協議が必要です)。
- 深基礎や杭を打ち、より安定した地盤まで建物の抵抗要素を確保する。
- 擁壁とは独立した土留め壁を設ける。
- 現在の擁壁を撤去し、必要な性能を持つ新しい擁壁を設置し直す。
Q3. 擁壁の「危険サイン」(ひび割れ・エフロ・漏水)を見つけた時、どこに相談すべきですか?
- 専門知識を持つ構造設計者や地盤技術者にすぐに相談してください。
まず、写真記録や簡単な傾斜測定、排水経路の確認などを行い、必要に応じて詳細な地盤調査(ボーリング、透水性試験、変位測定)を行われます。
同時に、検査済証や造成認定の有無を確認し、補修・更新・新設といった選択肢を、技術的な安全性、法令、そしてコストの三つの側面から評価・提案してくれます。
Q4. 2025年の四号特例見直しで、木造2階建ての設計実務はどう変わりますか?
- 従来、手続きが省略・簡略化されていた小規模な木造住宅についても、構造関係図書の提出と審査が原則として必要になります。
これにより、敷地条件、特に擁壁、がけ、地盤排水といった安全性に関する項目が確認申請の過程でより厳しくチェックされ、指摘や補正が増える見込みです。
構造設計実務では、計画の初期段階から擁壁の適法性、性能、維持管理の状態をセットで点検し、その情報を図面に明確に反映することが非常に重要になります。
まとめ
杉並区の擁壁崩壊事例で、建物の強度だけでなく、地盤、擁壁、排水といった敷地全体を一つの力学システムとして捉え、その安全に責任を持つことの重要性を改めて感じました。報道で指摘されたひび割れや漏水は、背面土の飽和や排水機能の低下を示しており、擁壁の滑動・転倒を誘発し得る危険なサインです。
実務においては、既存の二重擁壁(二段擁壁)や検査済証のない不適格擁壁を早期に洗い出すことが不可欠です。これらを適法性、性能、維持管理の三点から再評価し、「がけ条例」の離隔条件を前提とした最適な対策(深基礎、杭、新設擁壁など)を計画初期から織り込む必要があります。
特に、2025年の法改正で小規模木造でも構造関係図書の提出・審査が原則化されるため、敷地条件に起因する指摘は増加する見込みです。
ひび、エフロ、漏水、排水不良といった兆候を見つけたら、迷わず構造・地盤の専門家へ相談いただき、被害の未然防止に努めましょう。
>構造設計者に相談するなら「ストラボpartner」へ
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。