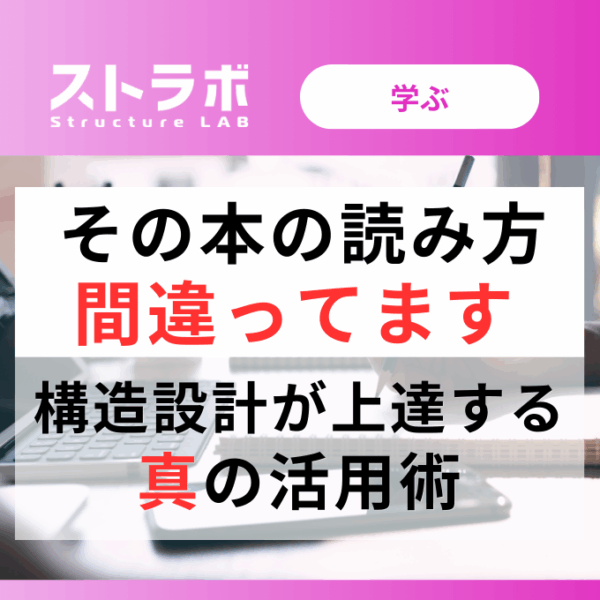建築物の安全性を確かめるために欠かせないのが「構造計算書」です。構造計算書には、地震・台風・積雪といった外力に住宅や建物が耐えられるかを数値で示す内容がまとめられており、建築確認申請で必要になる場合があります。
一般的な住宅でも条件次第では構造計算書の作成が推奨され、特に許容応力度計算などの手法は、基礎的な知識として学んでおきたい重要項目です。
建物の安全を守るには信頼できる構造設計者の存在が不可欠ですが、その理由や構造計算書の具体的な書類の中身を、本記事でわかりやすく解説していきます。
構造計算書とは?
構造計算書は、建築物の構造計算に関する概要、前提条件、計算結果などをまとめた公式文書です。
建物の骨組みが地震や風、積雪といった外部からの力に耐えられるか、検証した結果が記されています。
一定の規模以上の建築物においては、建築確認申請や構造計算適合性判定の際に提出が義務付けられています。
それらを記録した構造計算書は、ときにA4用紙で1,000枚を超える膨大な資料となります。
構造計算書の内容一覧|申請に必要な書類と記載項目
構造計算書は、建築確認申請や構造計算適合性判定時に必要となる重要な書類です。
内容は用いる計算方法や建物の規模によって異なりますが、主な項目は以下の通りです(規則1条の3 表三より抜粋)
構造計算チェックリスト
- 基礎・地盤説明書
- 荷重・外力計算書
- 保有水平耐力計算書/保有水平耐力計算結果一覧表
- 損傷限界に関する計算書/損傷限界に関する計算結果一覧表
- 剛性率・偏心率等計算書/剛性率・偏心率等計算結果一覧表
使用構造材料一覧表
- 使用構造材料一覧表
- 応力計算書/断面計算書/基礎ぐい等計算書/使用上の支障に関する計算書
- 屋根ふき材等計算書
- 安全限界に関する計算書/安全限界に関する計算結果一覧表
特別な調査又は研究の結果等説明書
- 部材断面表
- 層間変形角計算書/層間変形角計算書結果一覧表
- 積雪・暴風時耐力計算書/積雪・暴風時耐力計算結果一覧表
- 土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書
構造計算には、許容応力度計算をはじめ、保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答解析といった複数の計算方法が用いられます。
一定規模以上の建築物では、構造設計一級建築士にしか扱えない計算方法もあり、高度な専門性が求められます。
<参照>
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
許容応力度計算とは?構造計算書で確認できる内容と流れ
許容応力度計算は、建物に作用する力(固定荷重や積載荷重などの「長期荷重」、地震や台風といった「短期荷重」)に対し、柱や梁といった各部材がどれだけの力に耐えられるか(応力度)を検証する基本的な計算方法です。
許容応力度計算は大きく3つのプロセスに分かれます。
- 荷重計算:建物に作用する荷重を想定
- 応力計算:荷重が部材に与える影響をモデル化
- 断面算定:各部材の断面が安全性を満たしているかを確認
以上を踏まえて作成される構造計算書は、以下の流れでまとめられます。
- 一般事項:建物概要、設計方針、使用材料
- 個別計算:荷重計算、二次部材計算(小梁やスラブ等)、基礎の計算、別途詳細検討
- 一貫計算:柱・梁・壁の安全性をソフトで総合的に検証
一般住宅でも構造計算書が必要になる条件と注意点
構造計算書はすべての建物に作成が義務付けられているわけではありません。木造平屋で延べ床面積200㎡以下の新3号建築物については、一部、審査省略が認められています。ただし、都市計画区域内では建築確認・検査は必要です。
<参照>
国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
構造計算していない木造戸建住宅に潜むリスク!2025年「4号特例」改正を解説
https://tsuyoku.jp/yongoutokurei_kaisei/
しかし、仕様規定だけでは安全性を確保できない場合があり、実際に計算すると壁量不足が判明するケースも報告されています。また、以下のような住宅では構造計算の必要性が高まります。
特に以下のような住宅では、構造計算の必要性が高まります。
- 都市部の変形や狭小地での建設
:ねじれや偏心に加えて、塔状建物(縦横比が大きい)の場合は転倒の影響 - 多数の大きな開口部
:ねじれや偏心による影響 - リビング・ダイニング・和室等をまとめた大空間
:大空間を構成する部材の大断面化 - スキップフロアや吹き抜け
:水平剛性が不足することによるせん断伝達の影響
※上記の項目について、すべての建築構造物に該当します。
このように、構造計算書の要否は法的義務だけで判断すべきではなく、建物の安全性全体を考慮して検討する必要があります。
構造計算書は構造設計者へ依頼すべき理由
構造設計者の役割は、計算書や図面を作成するだけにとどまりません。
建築計画、コスト、安全性といった相反する条件を調整し、最適な骨組みを設計することが求められます。場合によっては構造上の検討を踏まえて建築計画を修正することもあります。
構造計算書偽装問題とは?姉歯事件の概要と教訓
2005年に発覚した構造計算書偽装問題(いわゆる姉歯事件)では、国土交通大臣認定のソフトで算出された結果が改ざんされ、耐震基準を満たさない建物が建設される事態に至りました。
膨大な計算書やコンピュータ依存の審査体制が、偽装を見抜けなかった一因とされています。
この事件は建築業界に大きな衝撃を与え、構造計算書の信頼性と、それを担う構造設計者の重要性が改めて認識されました。
建物の安全を守るためには、専門性と倫理観を備えた設計者に依頼することが不可欠です。
まとめ 構造計算書の役割と住宅に必要なケース
構造計算書は、建物が外力に耐えられるかを計算に基づいて証明する重要な書類です。
住宅であっても条件によっては作成が必要となり、単なる法的要件ではなく安全性確保の観点から判断することが大切です。
また、過去の偽装事件が示すように、専門性の高い分野であるがゆえに外部からのチェックが難しく、信頼できる構造設計者を選ぶことが建物の安全を確保する上で最も確実な方法といえるでしょう。
建物の安全をしっかり確保したい方は、信頼できる構造設計者とつながれる「ストラボnavi」や、安定した副業・独立を支援する「ストラボpartner」の無料登録をご活用ください。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。