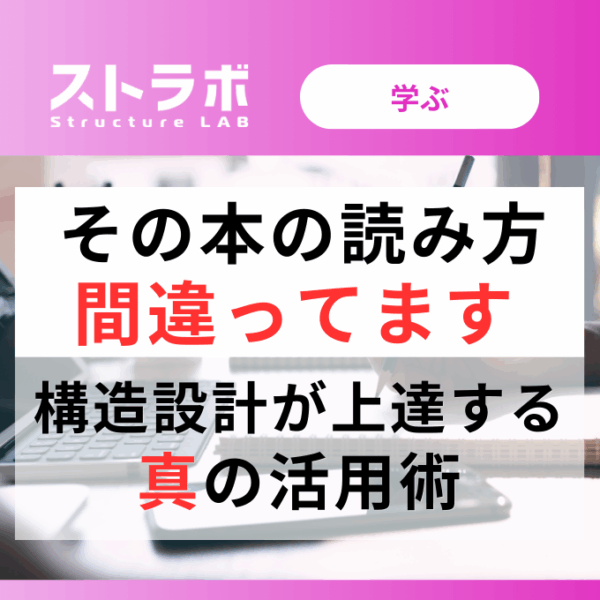人命や財産を守る「建築構造設計」の仕事。地盤調査から始まり、構造形式・材料の選定、構造計算や構造図作成、工事監理までその仕事は多岐にわたります。
高い専門知識と経験が求められ、社会的にも重要な役割を担っています。では、この仕事に就くためには、どのような資格が必要なのでしょうか。
建築構造設計に資格は必須? 無資格でも働ける範囲
結論からお伝えすると、構造設計事務所などで社員として勤務する場合、最初から特別な資格がなければ仕事ができない、という決まりはありません。その背景には、構造設計の資格の多くが「取得前に実務経験を積むこと」を前提としているからです。
では、無資格で構造設計の仕事をしたら違法になるのでしょうか?
構造設計者が目指す代表的な資格は建築士です。建築物の設計や工事監理は高度な専門性が求められるため、国が基準を設けて知識・技術水準を保証しています。資格取得前でも、設計補助業務として無資格者が業務に関わることは違法ではありません。ただし、無資格者が作成した設計図を、有資格者の監修なしに納品すると違法行為となります。必ず有資格者が全体の責任者として監修し、署名・押印をする必要があります。
つまり、無資格者でも設計補助は可能ですが、自らの判断で設計業務を行うためには建築士資格が不可欠です。
資格取得で広がるキャリア
「資格がなくても働けるなら、無理に取らなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、資格があるのとないのとでは、設計者としてのキャリアに大きな差が出ます。
|
短期的なメリット |
長期的なメリット |
|
勤務先によっては |
社会的信用が格段に上がる |
|
転職時に有利になる |
独立開業が可能になる |
|
専門性が評価され |
難易度が高い案件へ参加できる |
資格取得は、単なる手当や転職のしやすさだけでなく、キャリアの選択肢を広げ、特に独立開業を考えるうえで必須のステップです。建築士事務所の開設は二級建築士や木造建築士でも可能ですが、社会的評価や業務範囲の広さから一級建築士、構造設計一級建築士を取得しておくことで、より大きな仕事に挑戦できるようになります。
国家資格「一級建築士」とは
一級建築士は、国土交通大臣免許を受けて建築物の設計・工事監理を行う国家資格で、複雑かつ高度な建築物を含め、ほぼ全ての設計を担える基幹資格です。
建築士には以下の5種類があります。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
- 構造設計一級建築士(上位資格)
- 設備設計一級建築士(上位資格)
以上の建築士資格のうち、上位資格を除く3種(一級・二級・木造)は、設計可能な建物の規模や構造に違いがあります。
一級建築士の受験条件
令和2年3月の建築士法改正により、実務経験は受験要件から免許登録要件に移行しました。受験資格は学歴により異なり、大学卒で2年以上、短大(3年)卒で3年以上、短大(2年)や高専卒で4年以上の実務経験が必要です。
一級建築士の上位資格「構造設計一級建築士」とは
構造設計一級建築士は、一級建築士の中でも構造分野に特化した上位資格で、平成18年12月の建築士法改正によって新設されました。背景には、構造計算書偽造問題があり、建築物の安全性を担保するために制度が整備された経緯があります。
構造設計一級建築士にしかできない業務
法改正以降、一定規模以上の建物では、次のいずれかの対応が義務付けられています。
- 構造設計一級建築士が直接構造設計を行う。
- 他の一級建築士が設計した場合、構造設計一級建築士による「構造関係規定への適合性確認」を受ける。
この確認がないまま建築確認申請をしても、申請自体が受理されません。
適合性確認が必要な建物は、原則として一級建築士の業務独占に該当する建築物のうち、以下に分類されます。
- 高さ60mを超える建築物
- ルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算が必要な、高さ60m以下の建築物
関与が不要なケース
構造設計一級建築士の関与が不要な建物もあります。例えば、中小規模で構造安全性の確認が比較的容易な建築物の場合、一級・二級・木造建築士のみで設計可能です。しかし実際には、意匠・設備・構造の各分野が分業化されるのが一般的で、構造設計一級建築士は専門性の高さを証明する重要な資格といえます。
受験資格
構造設計一級建築士を目指すには、次の条件を満たす必要があります。
- 一級建築士資格を取得後、5年以上の構造設計実務経験を有する。
- 国土交通大臣登録の講習機関による講習を修了する。
その他の専門資格
構造計算適合性判定資格者
構造計算適合性判定資格者は、大規模または中規模の建築物について、構造計算が適正に行われているかを審査する専門家です。審査業務に携わるには、構造計算適合性判定資格者検定に合格し、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
判定員になるための条件
- 一級建築士資格を保有していること。
- 構造設計業務や確認審査業務など、合計5年以上の実務経験を有すること。
JSCA建築構造士
JSCA建築構造士は、一般社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)が認定する資格で、構造計画の立案から設計図書作成、構造分野の工事監理までを統括できる技術者を証明するものです。構造設計一級建築士の中でも、特に幅広い知識と豊富な実務経験を持つ、高度なエンジニアであることを社会に示します。
受験資格
- 構造設計一級建築士資格を保有していること。
- 責任ある立場での構造設計実務経験が2年以上あること。
- 構造監理業務の実務経験を有すること。
まとめ
建築構造設計に関わる資格の有無や種類、取得メリットについて解説しました。
- 構造設計の業務は無資格でも補助的に携われますが、自ら判断・責任を持つためには資格が必要
- 一級建築士や構造設計一級建築士などの取得は、独立や高難度案件の受注に直結する
- 資格取得には一定の実務経験が必須で、計画的なキャリア形成が重要
- 構造計算適合性判定資格者やJSCA建築構造士は、さらに高度な専門性を示す資格
資格取得やキャリアアップを考えている方は、ぜひストラボにご相談ください。ストラボでは、構造設計者専門の転職支援サービス「ストラボnavi」や、副業・独立支援サービス「ストラボpartner」など、あなたのキャリアをサポートする多様なサービスを提供しています。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。