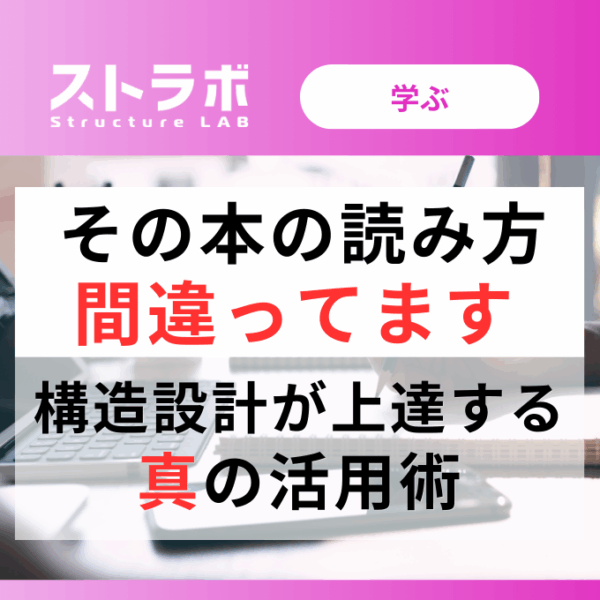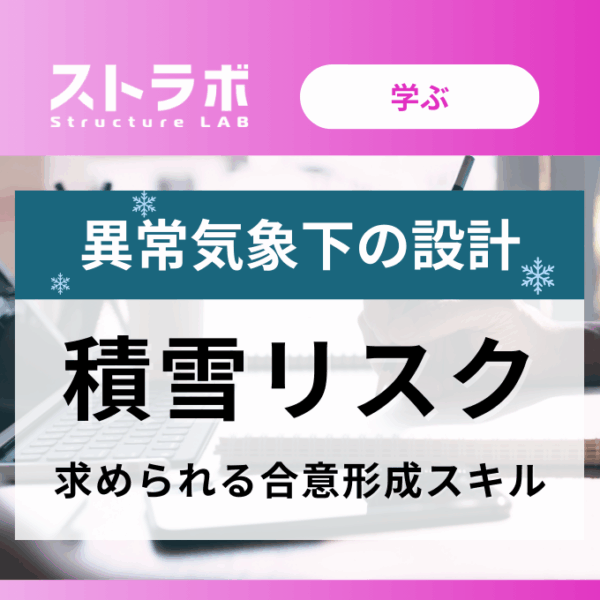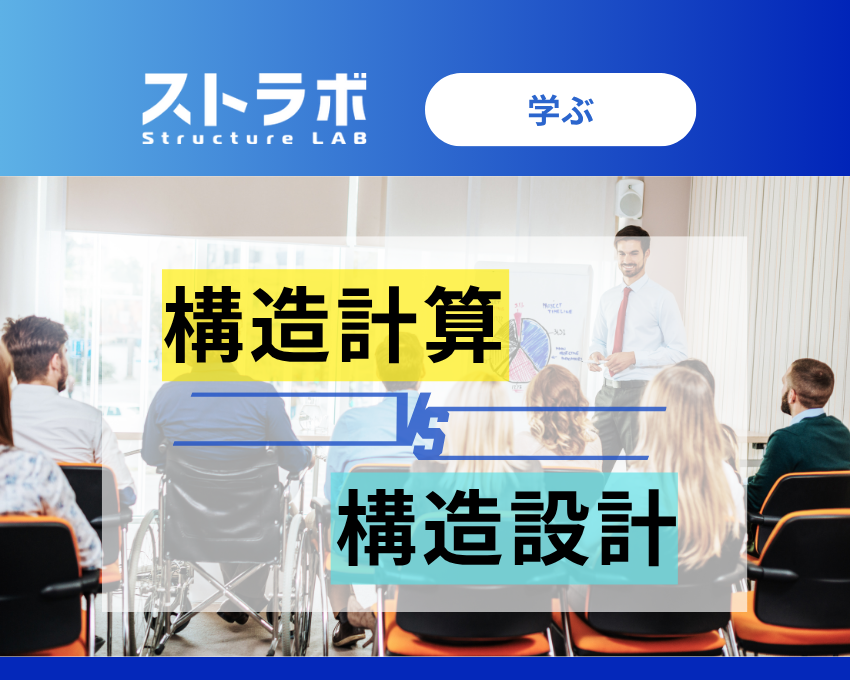
構造設計は設計判断、構造計算はその妥当性を数値で裏付ける検証です。
品質の最終確保は工事監理で担保され、施工者の是正と検査を経て完成します。
本記事では、構造設計者の役割、構造設計実務で広く用いられる構造計算ソフトや計算手法(許容応力度・保有水平耐力など)の使い分け、現場リスクの回避策を紹介します。
結論|「構造設計」と「構造計算」は役割が違う
構造設計は骨組みを定める設計判断、構造計算はその妥当性を数値で裏付ける定量検証です。
建物の安全性は、計算だけでなく設計判断と工事監理で現場まで担保して初めて完成します。
|
観点 |
構造設計 |
構造計算 |
|
目的 |
骨組み(基礎・柱・梁・壁)を計画し、空間要件と安全・コストを両立 |
想定荷重(自重・地震・風・雪等)の応力・変形を定量評価し妥当性を検証 |
|
主なアウトプット |
構造計画、構造図、仕様・要求性能 |
計算条件・モデル化、各種計算結果、断面検定、計算書 |
|
関与範囲 |
企画~実施設計~工事監理(施工段階の確認・是正) |
設計フェーズの検証(工事監理では前提と納まりの整合確認) |
|
代表的知見 |
設計基準・学会指針、BIM/CAD、標準詳細 |
許容応力度/保有水平耐力/限界耐力/時刻歴、FEM |
|
主なリスク |
空間・コスト・安全のバランス欠落 |
モデル仮定と現場納まりの齟齬により「計算通りにならない」 |
用途別|使い分けの着眼点(RC造/S造/木造/混構造)
- RC集合住宅:遮音・耐火・躯体コスト・スパンの折り合い。壁量・開口と設備経路の整合。
- Sオフィス・大空間:大スパン・可変性・制振の適合。柱位置とコア計画の整合。
- 木造(在来/中大規模):耐力壁配置・偏心・接合部ディテール・CLT等の面剛性の扱い。
- 混構造:層間変形の整合・剛性差の段落し・伝達ディテール。
意匠の空間要件×施工性×維持管理を同一テーブルで評価し、要求性能を数値化してから計算へ進むと、設計変更の手戻りを大幅に抑制できます。
<参照>J-SHIS 地震ハザードステーション(防災科研)
https://www.j-shis.bosai.go.jp/
代表的な計算手法の使いどころ
- 許容応力度計算:一般的な建物で広く用いる基盤手法。応力度が許容内かを確認。
- 保有水平耐力計算:構造特性係数等を用い、保有水平耐力が必要耐力を満たすかを評価。塑性余裕の確認に有効
- 限界耐力計算:応答スペクトルと等価線形化法等を用い、地震時の層間変形や損傷度を確認。改修方針検討にも有用。
- 時刻歴応答解析:具体的な入力地震動に対する時間領域応答を解析。特殊・高度な検討に適用。
- FEM(有限要素解析):局所的な応力・変形の把握、複雑な接合部や異形形状の検証に適する。
支点条件・剛域・減衰・剛性低下などモデル仮定と、安全率(クライテリア)の置き方で結果は変わり得ます。手法は“目的適合”で選ぶのが鉄則です。
<参照>
建築基準法(e-Gov法令)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
建築基準法施行令(e-Gov法令)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
日本建築学会『鉄筋コンクリート造建物の等価線形化法に基づく耐震性能評価型設計指針・同解説』
https://www.aij.or.jp/books/productId/692185/
工事監理と品質保証|“計算通りにならない”を現場で止める
配筋省略・継手位置不良・ボルト未締結などは、耐力低下の典型的な原因です。
工事監理では「配筋・建方・本締め・打設前後」の要立会い局面で、設計意図と現場納まりのズレを即時に是正指示し、施工者の是正・再確認を行います。
迷った場合は、その場で設計者に連絡し、影響評価と是正指示を行うのが鉄則です。
発注者が事前に用意すると良い資料
- 配筋要領図
- 仕口・柱脚詳細
- デバイス仕様書
- コンクリート配合計画書
- 溶接手順書
- 検査記録様式
発注者が専門家へ相談すべきケース
- 不整形大スパン
- 新工法採用
- 工程短縮で施工手順変更が想定される場合
<参照>令和7年版 防災白書(内閣府)
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r7.html
工事監理まで任せたい方は、ストラボpartnerへご相談ください!
依頼前チェックリスト
- 用途・規模・求める空間(スパン・階高・可変性)
- 敷地条件(地盤・隣地・風・積雪・関連告示の適用可否)
- コスト・工期・維持管理の制約
- BIM/CAD環境・希望するデータ互換条件
- 相談したい論点(構造種別の比較、制振・免震の適合、確認申請前の余裕評価 など)
アウトソーシング・増員を検討中の方へ
忙しい時に頼れる構造設計者を探す >> ストラボpartner
基礎から体系的に学び直したい方へ
構造計算の実務をオンラインで習得 >> ストラボschool
構造設計は設計判断、構造計算は定量検証、品質は工事監理で完結
本記事では、構造設計は骨組みと要求性能を決める設計判断、構造計算はその妥当性を数値で裏づける検証であることを整理しました。
計算手法は目的適合で選び、モデル仮定と安全率の置き方まで含めて整合をとることが重要です。
さらに、施工段階の工事監理で設計意図と現場納まりの乖離を是正してはじめて、性能・コスト・工期を総合的に最適化できます。
FAQ|構造設計・構造計算・全体のよくある質問
Q1. 構造設計者はどこまで関与しますか?
A. 企画段階の骨組み案から実施設計、施工段階の工事監理まで一貫して関与し、必要に応じて是正指示や再検討を行います。
Q2. 意匠・設備との調整で重視する点は?
A. 大スパンや開口計画、配管・ダクト経路、避難・防耐火要件と構造安全の両立です。
早期に要求性能を共有するほど手戻りが減ります。
Q3. コスト最適化はどの段階で行う?
A. 構造種別・スパン設定・標準化ディテールの選択など、基本設計段階が肝。
以降は計算・納まりと往復しながら微調整します。
Q4. どの手法を選べば良い?
A. 一般的には許容応力度計算が基盤です。
複雑な建物や高性能が求められる場合は、保有水平耐力計算・限界耐力計算、要部や特殊応答には時刻歴応答解析・FEM解析と「目的適合」で使い分けます。
Q5. 計算結果は設計者で違うの?
A. モデル化の仮定や安全率(クライテリア)の置き方に裁量があるため、結果は一致しないことがあります。
設計根拠の説明と第三者レビュー体制が重要です。
Q6. 既存建物の改修では?
A. 現況把握(図・配筋探査)→性能評価→補強方針(耐震・制震・免震)を選定。
施工段階の工事監理が成否を分けます。
Q7. 計算だけで品質は担保できますか?
A. できません。工事監理で実施工と設計意図の一致を確認し、乖離があれば是正して初めて品質が担保されます。
Q8. 第三者レビューは必要?
A. 不整形・大スパン・新工法採用時などは第三者レビューや部分解析を推奨します。
記録・写真台帳・ミルシートの整備は、竣工後の保全にも有効です。
<参照>
実務のための耐震診断マニュアル(東京都建築士事務所協会)
https://www.taaf.or.jp/about/docs/20170901manual.pdf
相談・お問い合わせ
案件の方針検討やネック解消の壁打ちはストラボpartnerへ、学習・育成はストラボschoolへ。
最短経路で次の一手を設計します。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。