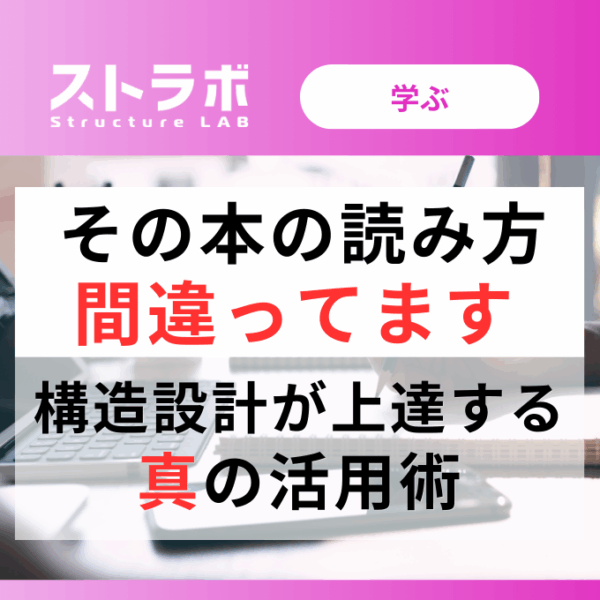建築構造とは、建物を支える骨組みそのもので、人々の生命や財産を守るための大切な基盤です。地震や台風など自然災害が多い日本では、建築構造の理解は安全性の確保に直結します。
構造形式や構造材料にはそれぞれ特徴や役割があり、その選択次第で建物の耐震性や快適性は大きく変わります。
本記事では、建築構造の基本的な考え方と種類をわかりやすく解説し、安心して暮らせる建物がどのように実現されているのかを紐解きます。
建築構造とは何か
建築とは、人が快適に暮らし、健康や生命、そして財産を守るための空間を計画・設計し、建て築く行為や、そのようにして建てられた建物のことを指します。
その中で「建築構造」とは、建物を地上や地下で安全に支えるための骨組みのことです。柱や梁、床板などで構成される骨組み全体を含み、力の流れや構造形式、使用する材料、架構方法など、多岐にわたる要素を網羅的に検討します。
言い換えれば建築構造は、建築物を支える「背骨」のような存在です。優れたデザインや機能を持っていたとしても、構造が不安定であれば安全とはいえません。
人が安心して暮らすためには、建築構造はなくてはならない要素なのです。
建築構造の役割と外力
建築構造の基本的な役割は、建物に作用する力から倒壊や大きな損傷を防ぐことです。
力には、建物に常に作用する重力由来の「自重」と、自然現象によって一時的に作用する「外力」の2種類があります。外力として代表的なものは以下の通りです。
【代表的な外力】
- 地震:建物の揺れによる倒壊・損傷、津波による流失、地盤の液状化など被害は多岐にわたる。
- 台風:強風で屋根や外装が破損し、大雨で土砂災害や浸水が発生。近年は大型台風による被害が拡大傾向。
- 積雪:統計上の予測を超える豪雪が発生することもあり、屋根や構造部材に大きな荷重がかかる。
- 竜巻:発生頻度は低いが予測が難しく、突発的に甚大な被害をもたらす。
これらの力は最終的に地盤に伝達されるため、地盤の強度(地耐力)も重要です。
すなわち建築構造を検討するとは「建物に加わる力を、いかに無理なく効率的に骨組みを通して地盤に伝えるか」を考えることに他なりません。
建築構造を形づくる要素
建築構造は「構造形式」と「構造材料」の2つの観点から整理できます。建物の用途・規模・コスト・性能に応じて、最適な形式と材料を組み合わせることが設計の基本です。
構造形式とは?一般的な構造形式の特徴
建物の「構造形式」は多種多様ですが、大きく分けると、柱と梁で力を伝える「ラーメン構造」と、壁や面材が荷重を負担する「壁構造」の2つに分類できます。この分類を理解することで、それぞれの特性や用途を整理しやすくなります。 以下に代表的な構造形式を紹介します。
ラーメン構造
特徴:柱・梁・床板で建物を支える形式。耐力壁に依存しないため、間取りや窓配置の自由度が高い。
利用例:中高層マンション、オフィスビル、スケルトン・インフィル住宅など。
注意点:柱や梁に大きな力が集中するため、断面設計や接合部の検討が重要。耐震性確保には精緻な構造計算が必須。
耐震壁付ラーメン構造
特徴:ラーメン構造に耐震壁を加えた形式。壁が水平力を分担するため、柱や梁の断面寸法を小さくできる。
利用例:集合住宅、事務所ビルなど。柱梁と耐震壁のバランスで耐震性能を高められる。
注意点:耐震壁の配置が偏ると建物がねじれ変形しやすい。意匠設計と構造設計の調整が重要。
ブレース構造
特徴:柱・梁に加えて斜材(ブレース)を設置し、水平力に抵抗。軽量で効率的に耐震性を確保できる。
利用例:鉄骨造の中低層建物、工場、倉庫、商業施設。
注意点:ブレースが配置された面は開口制約があり、設計自由度が低下。意匠デザインと機能の両立が求められる。
トラス構造
特徴:部材を三角形に組み合わせ、ピン接合で軸力のみを負担。少ない材料で大スパンを可能にする。
利用例:体育館やスタジアムの屋根、橋梁、展示場など大規模空間。
注意点:接合部設計・施工精度が性能を大きく左右。形状が複雑になると設計・施工難易度が高い。
壁式構造
特徴:柱や梁を設けず、耐力壁が荷重を負担する形式。シンプルで安定性が高い。
利用例:低層マンション、学校、病院など主に5階建て以下の建物。
注意点:開口や間取りの自由度が制限される。大空間や変則的なプランには不向き。
シェル構造
特徴:薄い曲面板(シェル)を用いて荷重を分散。軽量ながら強度が高く、美しい造形が可能。
利用例:ドーム建築、美術館、宗教建築、スタジアム屋根など。
注意点:高度な設計技術と施工精度が必要。コストが上がりやすい。
構造材料とは?主な構造材料の特徴
建物に使用される「構造材料」は、建物の種類や用途、求められる性能に応じて使い分けられます。
例えば高層ビルでは「鋼材」が選ばれることが多いです。重い材料を用いれば構造的に不効率で経済性も損なわれるため、軽量で強度の高い鋼材が適しています。
一方で、日本の伝統的な住宅建築では「木材」が主流です。
木材は加工性に優れ、スケール感にも合致する素材として古くから利用されてきました。また、マンションのように遮音性や集合住宅としての快適性が求められる建物には「鉄筋コンクリート」が多く用いられます。
このように構造材料は用途や性能条件によって最適解が異なります。どの材料にもメリットとデメリットがあるため、それぞれの性質を十分理解し、設計に活かすことが重要です。
鋼材(鉄骨)
特徴:高強度で靭性に優れ、鉄筋コンクリートより軽量。工場生産が可能で施工精度が高い。大スパンや高層建築に有利。
利用例:超高層ビル、商業施設、工場、倉庫など。
注意点:腐食しやすく、防錆処理が不可欠。火災に弱いため耐火被覆などの対策が必須。
木材
特徴:軽量で加工が容易。調湿作用や温かみのある質感を持ち、環境負荷が低い。
利用例:戸建住宅、低層アパート、CLTを利用した中規模木造建築。
注意点:燃えやすく、強度のばらつきも大きい。防火・防蟻処理や含水率管理が必要。
鉄筋コンクリート(RC)
特徴:鉄筋の引張強度とコンクリートの圧縮強度を組み合わせた材料。耐火性・遮音性に優れ、設計自由度が高い。
利用例:マンション、学校、病院、公共施設など。耐震性・耐久性を重視する中高層建物に多用。
注意点:自重が大きく基礎に負担を与える。施工品質や養生期間が性能を大きく左右。
建物構造の安全性は構造体以外の要因にも注意
建築物の安全性は構造体だけでなく、非構造部材や仕上げ材、家具の安全性にも左右されます。近年の地震では天井の落下や壁仕上げ材の剥離、家具の転倒による人命被害が報告されています。
構造形式ごとに地震時の特性は異なります。
- 壁式鉄筋コンクリート造:変形が小さく強度は高いが、加速度が大きく家具転倒リスクが増す。
- S造(鉄骨造):加速度は小さいが変形は大きく、非構造部材や仕上げ材の破損リスクが高まる。
つまり、建物の安全性を確保するには構造体だけでなく、内装・設備・家具までを含めたトータルの視点が欠かせません。設計者は構造形式と非構造部材の特性を理解し、両者のバランスを取ることが重要です。
まとめ
本記事では建築構造の基本的な考え方、代表的な構造形式と材料の特徴、さらに非構造部材も含めた安全性確保の視点について解説しました。
建築構造は、建物の耐震性・耐久性・快適性を決定づける重要な要素です。構造設計者は構造形式や材料の特性を理解し、多角的な条件をバランスよく考慮して、利用者が安心して暮らせる空間を設計する責任を担っています。
建築構造の基礎から実務に役立つ知識、キャリアやスキルアップの最新情報は、「ストラボ」の無料会員登録でご覧いただけます!
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。