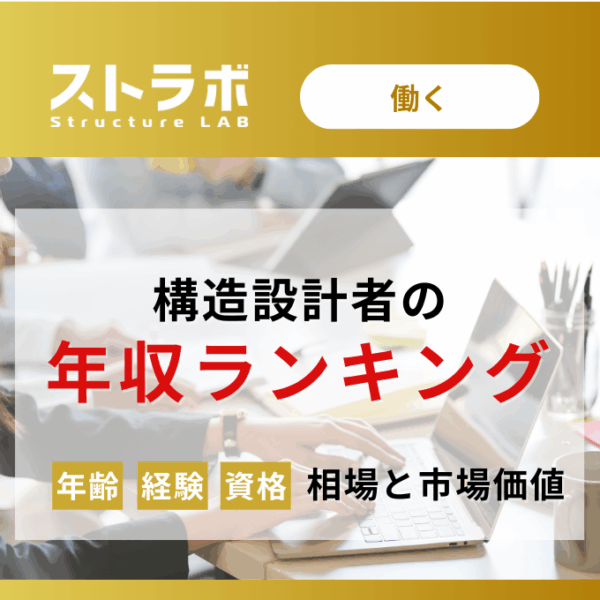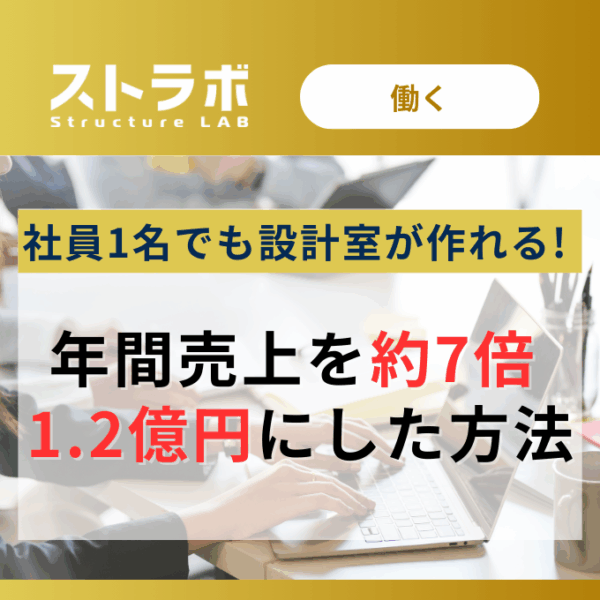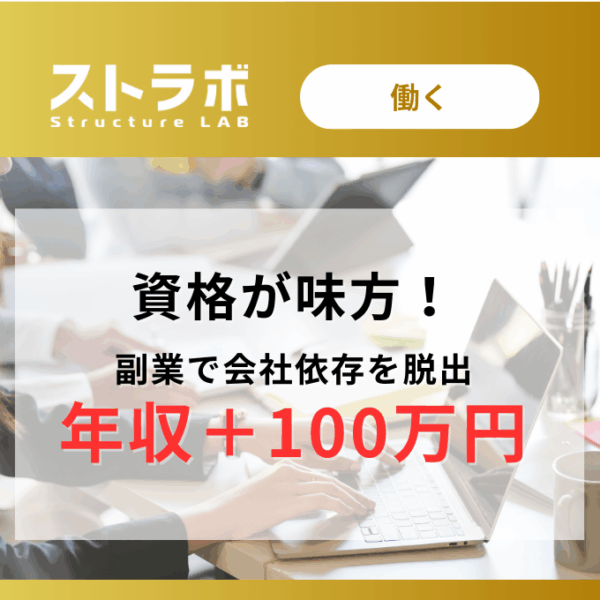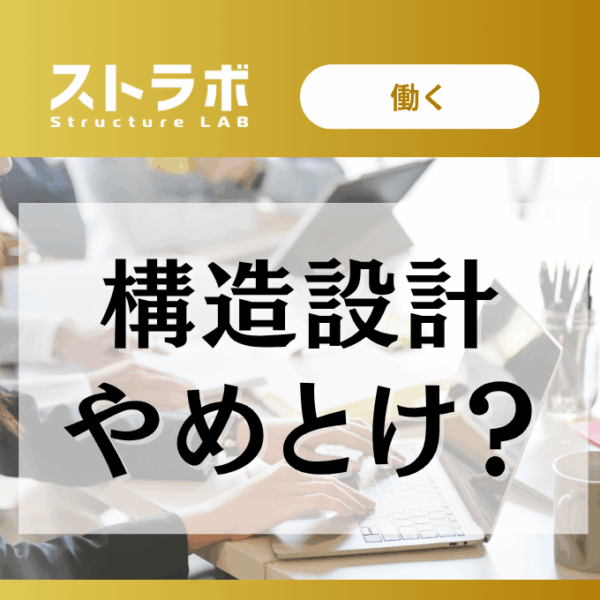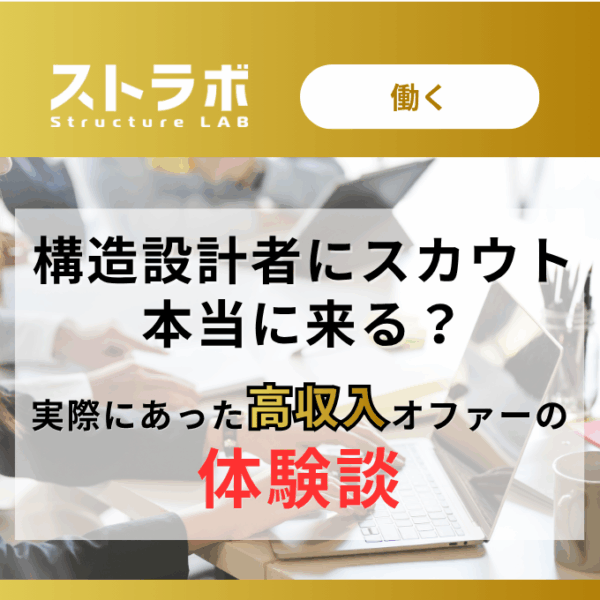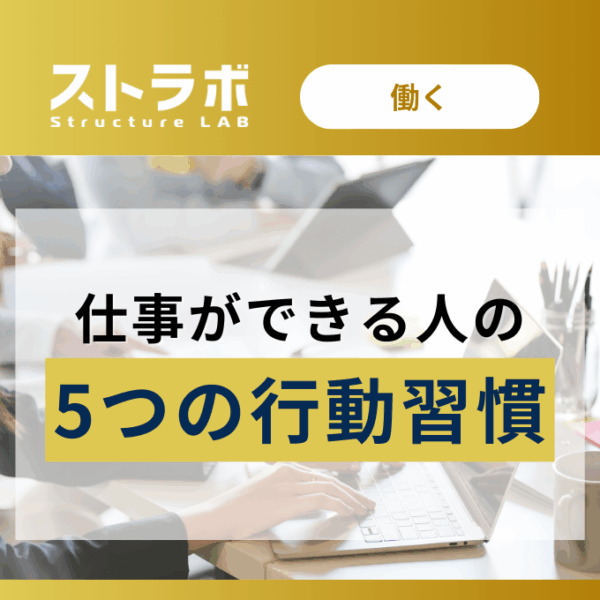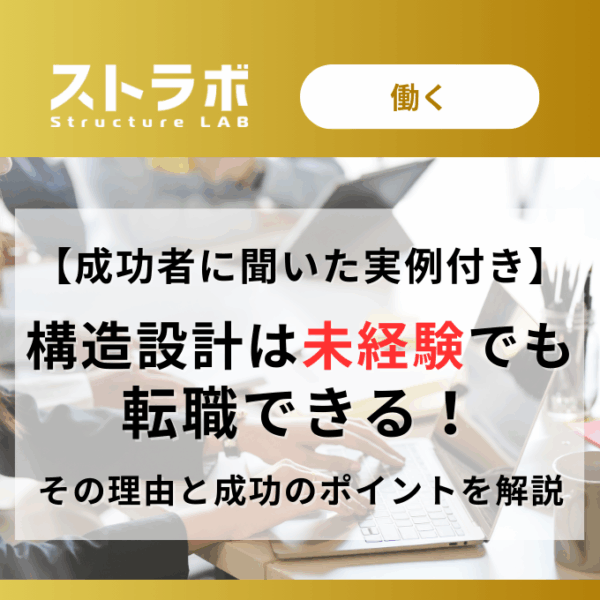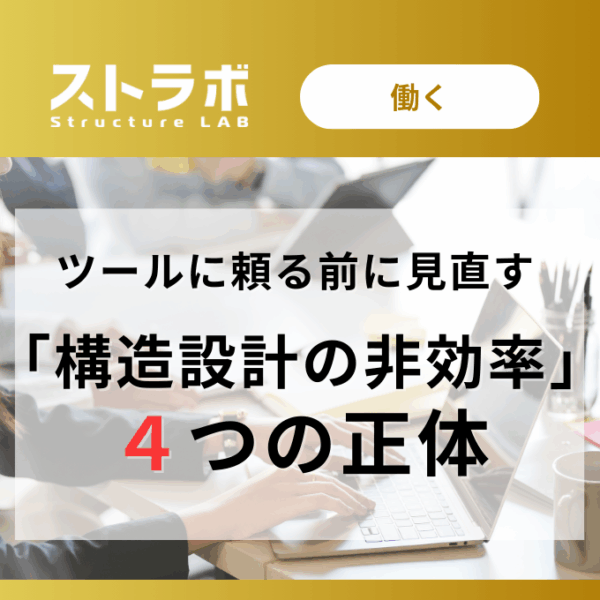構造設計事務所やゼネコン構造設計部で経験を積んできたけれど「このまま会社員でいいのか?」とモヤモヤしたことはありませんか?「いつかは自分の設計をしたい、でも独立して大きな借金や失敗をするのは絶対に避けたい…」その気持ち、痛いほどよく分かります。
独立は決して大きな賭けではありません。実は、初期投資の不安なく、あなたの好きな設計を長く続けるための「現実的な選択肢」のひとつです。
この不安を解消し、構造設計で独立・起業するための具体的なステップをお伝えします。
構造設計者が今すぐ独立・起業を考えるべき理由
「いつかは自分の設計を、自分の裁量でやってみたい」と考えている構造設計者にとって、まさに今が動き出すチャンスです。
構造設計業界は深刻な人手不足が続き、技術力のある設計者の需要が高まっています。会社の枠を超え、自分の専門性をそのまま“価値”に変えられる環境が整いつつあるんです。では、なぜ“いま”が構造設計者にとって独立・開業しやすいタイミングなのかを見ていきましょう。
業界全体が人手不足で、構造設計者の独立チャンスは過去最大
建設業界は今、人手不足が続いています。
国土交通省の調査でも、就業者数が減少し続けていることが明らかとなっており、構造設計業界でも若手が少なくベテラン設計者が現場を支えています。
これは、独立・開業を目指す構造設計者にとって本当にラッキーな流れです。
構造設計の需要に対して構造設計者が足りていません。
<参考>
国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001493958.pdf
働き方改革で在職中から「準備を進める独立」ができる
独立・開業の後押しとなっているのが「働き方改革」です。
労働時間の見直しや副業・兼業の容認など、働き方の自由度が広がったことで、在職中の時間を使って独立の準備を進める人が増えています。
焦って退職する必要はありません。名刺づくりやポートフォリオの整理、見積書のテンプレート作成など、まずは“仕事を受ける準備”を整えておくことが大切です。
こうした積み重ねが、独立後の安定したスタートにつながります。
構造設計特化のマッチングサービスで「人脈なし」でも仕事が取れる時代に
「人脈や紹介がないと独立は難しい」とよく言われていますが、建築業界も例外ではありません。
新たな受注先の開拓は、独立開業後の大きな課題になることが多いです。
そこでおすすめなのが、構造設計に特化したビジネスマッチング「ストラボpartner」です。

スキルや実績を登録すれば、経験や得意分野に合わせて企業から依頼を受けることができ、年間契約で、独立後も毎月の定額報酬を得ることも可能です。
リスクを最小化!構造設計者が独立前にやるべき準備6 5ステップ
「いつかは独立したい」と思っていても、何から始めればいいのか分からない方は多いのではないでしょうか。
独立は“退職してから考える”ものではなく、会社員のうちから少しずつ進められる準備がたくさんあります。独立前にやるべき5つの準備を紹介します。
副業から始める
副業を始めるにあたり、まずは就業規則を確認し、副業の可否、申請の必要性、利益相反や守秘義務に関する規定を把握しましょう。
本業と競合しない案件に限定し、会社の設備やデータは使用せず、私物のパソコンと自前のクラウドサービスなどで完全に分離して作業すると安心です。
契約に際しては、著作権や成果物の帰属、再委託の可否などについて明確に定めておきましょう。
始め方はスモールスタートを心がけ、夜間や週末を利用した月5〜10時間程度の稼働から案件を受注をスタートするのがおすすめです。
また、年間売上の見込みに応じて、税務署への開業届やインボイス制度への登録の要否を判断します。
副業を本格的に始める際には、見積書や請求書は屋号名義と専用口座で統一し、支払条件も明確に定めておきましょう。
このように、実際の稼働時間、単価、顧客との相性を小規模で検証し、手応えのある「勝ち筋」だけを広げていくことが重要です。
お金の安心:生活資金と仕事環境を整える
独立・起業したての時期は、正直言って収入はジェットコースターのように不安定になりがちです。
だからこそ、最低でも半年分の生活費、できれば1年分を「心の余裕代」として確保しておきましょう。
貯金は、焦らず案件を選べる最高の保険になります。
あわせて、作業環境も整えておきましょう。
パソコン、構造計算ソフト、ネット環境も、独立後すぐ使えるように準備しておくとスムーズです。
軸を定める:独立・起業の目的と「得意分野」を明確にする
独立を考える「本当の理由」は何ですか?お金のためだけではないはずです。
「設計者としての魂」となる目的がハッキリしていないと、独立後に「何のために働いているんだろう」と必ずブレてしまいます。
あわせて、自分の得意分野を整理しておきましょう。
過去に携わった案件の設計実績(建物用途・延床面積・構造種別など)をまとめておくのがおすすめです。
「どの分野で勝負できるか」を明確にすることが、独立後のあなたの強みになります。
人とのつながり:意匠設計者や他分野との人脈を広げる
独立・起業前から、意匠設計者・施工担当者・確認検査機関など、将来一緒に仕事ができそうな人との関係を築いておきましょう。
建築業界の勉強会やセミナーに参加する、SNSで建築関係者と交流するなど、小さな接点が後に大きなチャンスのきっかけになることもあります。
経営者マインド:税務・契約・社会保険の基本を学ぶ
独立すると「経営者」としての知識が嫌でも必要になります。
見積り、契約、請求、税金、社会保険など、最低限の仕組みを理解しておくだけで独立後も楽になります。
日本建築士会連合会や自治体の創業セミナーを活用して、経営の基礎を学んでおくと安心です。
また、将来的に相談できる税理士や社労士を早めに見つけておくことも重要です。
事務作業:すぐに契約できる体制を整える
いざ独立・起業を決意したときにスムーズに動けるよう、事務的な準備もしておきましょう。
在職中に進めておくのがおすすめな内容は、次の項目です。
- 名刺のデザイン、仕事用メールアドレスの作成
- 見積書・請求書テンプレートの作成
- 契約書のひな形の作成
- 事業用口座の開設準備
- 建築士事務所登録
- 開業届または法人登記の準備
初期投資0円?構造設計事務所を「机ひとつ」で開業する方法
「独立」というと、立派なオフィスや高価な設備を構えるイメージがあるかもしれませんが、構造設計の仕事はパソコンとネット環境さえあれば始められます。
初期投資を最小限に抑えることで、リスクをかけずに事務所を立ち上げましょう。
初期費用の現実:構造設計の独立は「30〜50万円」でスタート可能
独立初期に必要な資金は、設備や環境によって変わりますが、最低限の機材・構造計算ソフト・通信環境を整えるだけなら30~50万円程度が目安です。
「思ったより現実的」と感じられる金額なので、構造設計者が独立を具体的に検討しやすいのではないでしょうか。
- 高性能PC・モニター:約20〜25万円
- 構造計算ソフト(月額サブスク1〜2本):約2〜4万円/月
- CADソフト(Jw_cadなど無料〜低額サブスク):0〜1万円/月
- 通信環境・業務ツール(Google Workspace、Chatworkなど):約1万円/月
- 建築士事務所登録費:1.5〜2万円前後
こうして具体的な内訳を見てみると、「まずは小さな一歩から、必要なツールを少しずつ整えていこう」という形で十分スタートできることが分かります。
大きな初期投資で身動きが取れなくなる心配はありません。
構造計算ソフトは「月数万円のサブスク」で十分
構造計算ソフトは高額なので正直一番ネックですよね。
でも安心してください。
いきなりSS7やBUILD一貫、BUSといった一貫構造計算ソフトのライセンスの一括購入ではなく必要なソフトだけを月額で借りられるサービスが充実しています。
初期は「月数万円のサブスク」で十分です。
この柔軟性が、小規模独立の最大のメリットです。
【構造計算ソフト選定のポイント】
独立・起業初期に大切なのは、「過去の実績で使い慣れたソフト」を選ぶことです。
- 一貫構造計算ソフト(SS7、BUS、BUILD一貫など):主要なソフトは高価ですが、月額利用や期間限定ライセンスでコストを抑えましょう。
- CADソフト:AutoCADやRevitの永久ライセンスは高いため、無料のJw_cadや、低価格な年間サブスクリプションを選ぶのが現実的です。
- 応力解析ソフト:より専門的な解析が必要な場合のみ、スポットで利用できるサービスを検討しましょう。
自宅やシェアオフィスを活用して、固定費を「ゼロ」に近づける
最初の一歩は「どこで仕事をするか」です。
おすすめは、自宅のワークスペースや、必要に応じて使えるシェアオフィスを活用する方法もあります。
まずは“ひとりで集中できる環境”を整えることが最優先。無理にオフィスを借りて毎月の固定費を増やす必要は全くありません。
建築士事務所登録の手続きと費用
自分名義で設計業務を請け負う場合、「建築士事務所登録」は必須の手続きです。
- 費用
都道府県や登録の種類(一級建築士・二級建築士・木造建築士)によって異なりますが、建築士事務所登録手数料は数万円(おおむね15,000円〜20,000円程度)が一般的です。
また、登録後は5年ごとに更新が必要です。 - 準備
申請には「管理建築士の資格証明(一級建築士証など)」や「事務所の図面」「業務を行うために必要な機器の保有証明(PC、ソフトなど)」が必要です。 - タイミング
在職中に準備を進め、独立のタイミングに合わせて申請するとスムーズです。
ただし、押印を行わず他社からの外注(下請け)のみを行う場合は、契約主体が自分ではないため、登録が不要なケースもあります。
将来を見据えて、早めに準備を始めましょう。
<参照>
一般社団法人東京都建築士事務所協会
https://www.taaf.or.jp/regist/01.html
構造設計の独立は「最低限の初期投資」で始める
構造設計に必要な機材は、実はそれほど多くありません。
独立・開業は資金繰りのためにも「無理なく回せる範囲」で揃えることが、初期費用と 経営リスクを抑える最大のポイントです。
- ノートPCまたはデスクトップPC(外部モニターは一台からでOK)
- 高速インターネット環境
- 無料・低コストの業務ツール(Google Workspace、Chatworkなど)
独立後の不安を解消!起業後90日で仕事の波を安定させるロードマップ
独立を決意して最初の3か月は、いわば「立ち上げ期」です。
焦らず、着実に“仕事が回る仕組み”を整えることが大切です。
1週目:【即日稼働】名刺交換と挨拶メールで独立を周知する
まずは、準備してきた名刺・メールアドレス・請求書テンプレートなどを実際に使える状態に整えましょう。
独立を知らせる挨拶メールを、前職で関わった意匠設計者や取引先に送るのもこのタイミングです。
合わせて、契約書のテンプレートを整え、「いつ依頼が来ても案件を受注できる」状態を作ることがスタートラインです。
2~4週目:【実績づくり】小規模な外注・スポット案件で信頼を獲得する
最初から大きな案件を狙うより、まずは小規模な外注・スポット案件から始めましょう。
納期が短くリスクも低い案件ほど、経験を積みながら信頼を得るチャンスになります。
初期は「早く・正確に・丁寧に」の3点を徹底してください。この積み重ねが、リピートや紹介につながるのです。
1〜2か月目:質の高い仕事で「リピート依頼」につなげる
案件が終わったら、必ず依頼元にフィードバックをもらいましょう。
構造設計の世界では、“納期と品質を守ること”が最大の営業です。
一つひとつの仕事・案件を丁寧に仕上げることが、次の依頼を生む最短ルートだと肝に銘じてください。
3か月目以降:安定期に法人化・チーム化を検討する
収入と稼働が安定してきたら、次のステップとして法人化やチーム化を検討しましょう。
個人事業から法人化することで取引範囲が広がり、信用力も向上します。
案件が増えてきたら、信頼できる外注パートナーや協力事務所と協業体制を作ることで、「無理なく仕事を回す仕組み」が生まれます。
仕事が途切れない!構造設計者の独立後に必要な3つの要素
独立して構造設計を続けていくためには、技術力だけでなく、信頼を得るための資格・スキル・人脈が欠かせません。
ここでは、独立後に安定的に仕事を受注するために特に重要な3つの要素を整理します。
資格:一級建築士・構造設計一級建築士は「信頼の担保」と「受注範囲」を広げる
独立後に大きな支えになるのが、国家資格による信頼性です。
特に「一級建築士」「構造設計一級建築士」は、企業や自治体との契約条件に直結し、受注可能な案件の範囲を決めます。
資格は「技術の証明」だけでなく、「責任を持って任せられる相手」として認識されるために絶対に必要なものです。
スキル:コミュニケーション力・提案力・マネジメント力が欠かせない
独立後は、お客様や関係者と直接やり取りしながら仕事を進める力が求められます。
- コミュニケーション力:意匠設計者や施工担当者と円滑に協議し、構造の意図を正確に伝える力。
- 提案力:依頼内容や予算を踏まえ、最適な構造計画や進め方を提示する力。
- マネジメント力:複数の案件のスケジュール、品質、コストをしっかり管理し、責任を持ってやり遂げる力。
独立後は「技術力の高さ」だけでなく、こうした人と仕事を動かす力が、安定したキャリアを築くための土台になります。
人脈:意匠設計との信頼関係と、構造設計者同士の協業ネットワークを築く
独立後の安定は、意匠設計者や他分野との信頼関係と、構造設計者同士の協業ネットワークに大きく左右されます。
また、構造設計の現場では、構造設計者同士の協業も重要です。
あなたが倒れた時の「セーフティネット」としても、信頼できる受発注元や協業先を見つけておくことが、安定経営の大きな助けになります。
営業が苦手でも大丈夫!構造設計者が自然と仕事を増やす3つの方法
構造設計の仕事は、“売り込む”より“信頼される”ことで広がっていきます。営業が苦手でも無理なく始められる3つの方法を紹介します。
1:既存の知人・意匠設計事務所からの紹介が最強の営業
最初の仕事は、意外と身近なところから生まれます。
会社員時代のつながりや、以前担当した案件で知り合った意匠設計者からの紹介など、「これまでの人脈」こそ最も信頼できる営業ルートです。
意匠設計事務所は「対応が早くて安心できる構造設計者」を探しています。
独立したことを丁寧に伝え、名刺や簡単なポートフォリオを添えて知らせておくだけでも、声がかかるきっかけになります。
加えて、杭業者も丁寧な対応や高い技術力を持つエンジニアを個人名で把握しています。
建築の世界では、どこから紹介が来るか分からない、それだけ可能性が広がっています。
だからこそ、日々のコミュニケーションを大切にしましょう。
2:構造設計特化型マッチングサービスを活用し、安定的に案件を受注する
知人からの紹介や付き合いのある建築業界や意匠設計事務所からの受注にも限界を感じ、新規開拓に悩む声も多く聞かれますが、最近は、構造設計の案件をオンラインで獲得できる仕組みも整いつつあります。
中でも「ストラボpartner」は、構造設計に特化したマッチングサービスです。
構造設計の実績を登録すれば、あなたのスキルに合う依頼を直接受けられます。
3:現場の工夫や実績をWebやSNSで発信して信頼を積み上げる
もう一つの有効な手段が、「自分の設計スタイルを発信すること」です。
X(旧Twitter)やLinkedInなどで、
「こういう構造の工夫をしました」
「ここで安全性とデザインを両立できました」
といった現場目線の投稿は、同業者や意匠設計者の目に留まり、思わぬ紹介につながることもあります。
単なる営業ではなく、“安心して任せられる情報を整える”イメージで進めるのがポイントです。
独立後に失敗しないための「落とし穴」と確実に避ける3つの対策
独立は、決して勢いだけでうまくいくものではありません。技術力があっても、準備や方向性を誤ると、思わぬところでつまずくことがあります。
1:資金ショート!「やりたくない設計」でも受けざるを得なくなる
独立初期に最も多いのが、「資金が続かない」ケースです。
構造設計の仕事は、契約から入金まで時間がかかることが多く、報酬が手元に入るまで1〜2か月以上のタイムラグがあるのが一般的です。
理想は「半年分の生活費+運転資金」を用意することですが、貯金が尽きて焦ってしまう人もいます。
資金に余裕がないと、「やりたくない設計」でも受けざるを得なくなる。
これが最も悲しい失敗パターンです。
資金は「焦燥感を避けるためのコスト」だと考えてください。
2:「何でもやる」はNG!得意分野を明確にしないことによる品質低下・疲弊
独立後の失敗でよくあるのが、「何でもやろうとして疲弊する」パターンです。
構造種別(RC造・S造・木造)や建物用途を明確にしないまま動くと、対応範囲が広がりすぎて、結果的に効率も品質も下がってしまいます。
最初は、自分が最も得意でスピードを出せる分野に絞ることが大切です。
得意分野の明確化は、安定して働くための最も現実的な戦略です。
3:経営知識の不足による「税金・保険」での想定外の出費
構造設計者は技術職のため、経営や税務に苦手意識を持つ人が多いです。
しかし、独立後はすべての経営責任があなたに降りかかります。
- 落とし穴の例
確定申告の知識不足で想定外の税金が発生する
加入すべき社会保険や年金制度(国民健康保険や国民年金など)の選択を間違える
仕事に必要な経費の計上漏れで損をする
など。 - 対策
開業と同時に信頼できる税理士を探すことは、技術職の独立における最優先事項の一つです。
月数千円〜の顧問料は「安心を買うための必要経費」だと割り切りましょう。
専門家に相談し、制度を理解しておくことが、独立後の長期的な安定につながります。
まとめ|構造設計者がリスクを抑えて独立・起業を成功させるために
構造設計者の独立は、「安定を手放す」ことではなく、“自分の理想の働き方を選ぶ”という前向きな選択肢です。
まずは副業から小さく始めるのも有効な一手。在職のまま実績や相性を検証し、勝ち筋だけを拡張できます。
独立と聞くと、資金や営業、人脈の不安が浮かぶかもしれません。
しかし、構造設計特化のマッチングサービス「ストラボpartner」を活用すれば、会社員の延長線上からでも経営リスクを抑え、副業→スポット→年間契約と段階的に独立の準備を進められます。
「ストラボpartner」とは構造設計に特化したマッチングサービスで、仕事を発注したい構造設計事務所や建設会社の構造部と、受注したい構造設計者(個人事業主・建築士 事務所)をつなぐプラットフォームです。
登録すると、構造種別・対応範囲・経験年数などをもとに、自分のスキルに合った案件情報が届き、条件が合えばスポットまたは年間での契約・受注ができます。
副業で実績を積みたい方や独立・開業初期の構造設計者はもちろん、安定した案件を確保したい小規模事務所にもおすすめです。
構造設計者にとっての独立は「挑戦」ではなく、好きな設計を長く続けるための選択肢です。
焦らず、自分のペースで準備を進めながら、 “好きな設計を長く続けられる”働き方を形にしていきましょう。
監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)
株式会社ストラボ 代表取締役
オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。
2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。
構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。